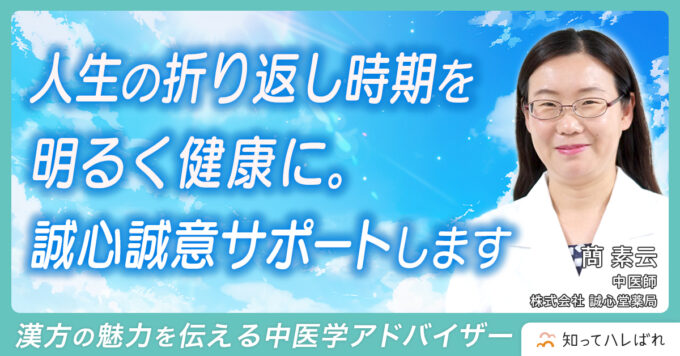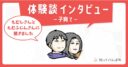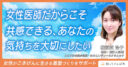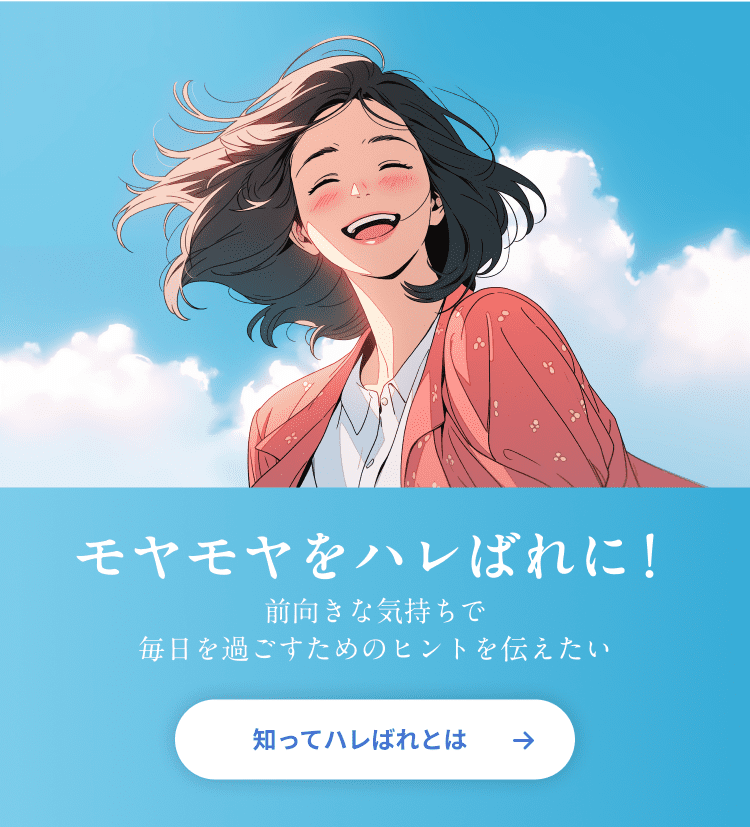生理をコントロールして、自分らしく生きる。人生であらゆる選択肢を選べる基盤づくりをお手伝い【医師 横須賀 治子】
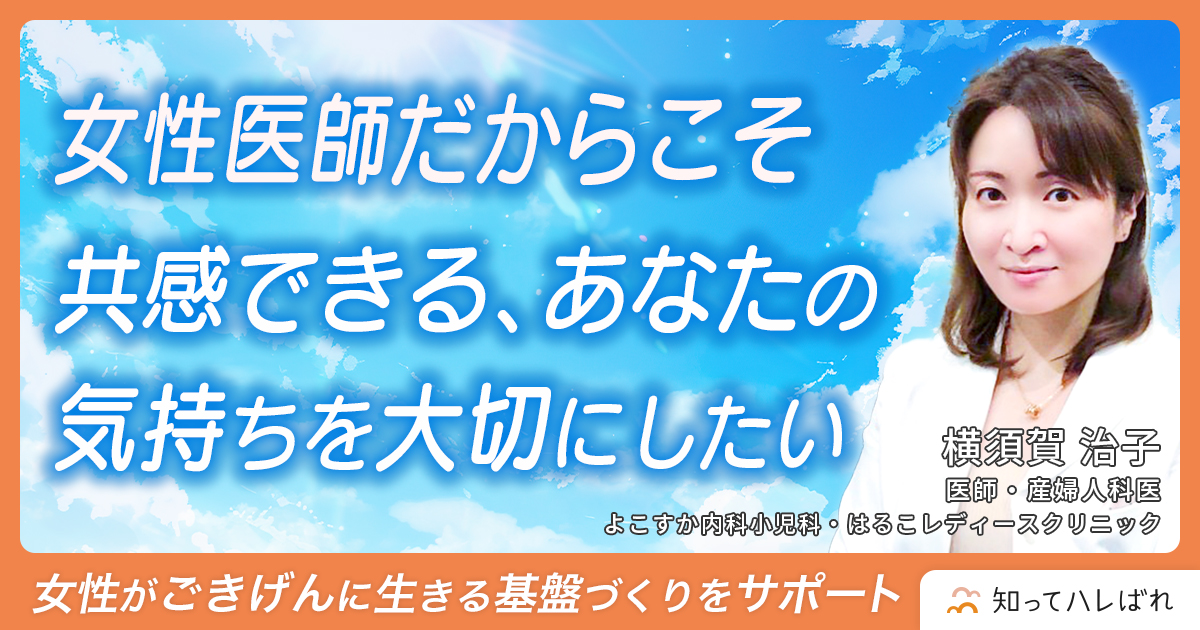
目次
育児との両立を乗り越えて産婦人科医へ
―産婦人科医を志したきっかけを教えてください。
私自身が小児喘息を持っていたこともあって、小さい頃から医師という存在に憧れていました。当初は小児科を志して医学部に進学しました。
しかしながら、研修医として働き始めてすぐに妊娠し、子育てと両立しながら医師としてのキャリアを考えることになりました。出産後に復帰し、研修医として小児科を回った際、泣いている子どもの姿を見るのもつらく、採血さえできなくなってしまったんです。小児科への憧れはありましたが、「子どもを診るのは難しいかもしれない」と思うようになりました。
その後、他の診療科への進路をどうするか迷っていたのですが、研修の最後に産婦人科を回ったとき、お産の現場に立ち会いとても感動しました。「おめでとうございます」と心から言える医療は産婦人科だけかもしれないと思い、「この道に進もう」と決意しました。
―子育てをしながら研修医としてお仕事をされていたとは、想像以上に大変そうです
そうですね。当時は、今のように周囲の理解が十分ではありませんでした。救急の当直の予定を組む際、日程の希望を伝えて調整を申し出たのですが、子育ての状況を理解してもらえず、一部の医師たちに「あなただけわがままを言っている」と非難されてしまったこともありました。ベビーシッター代で月に数十万円かかることもありました。
ただその時は、まず医師としての研修をやり遂げることを第一に考え、頭を下げながら周囲を頼ったり、貯金を崩したりしながらなんとか両立してきました。周囲の支えがあったからこそ乗り越えられたことには感謝しかありません。
今は経営の立場になって、スタッフの働き方に目を向けることも増えました。時代も大きく変わったなと感じています。現代はむしろ社会全体として「子育て中の従業員を最優先に」という風潮が強くなっていて、それは素晴らしいことだと思いますが、その反面、独身や子どもがいないスタッフがそのしわ寄せを受けてしまうケースもあるのではないかと気になっています。
それぞれの人にとって大事な事情があるのだから、独身でも既婚でも、子の有無も関係なく、休む理由に優劣をつけずに、「お互い様」とそれぞれが感謝し合える環境づくりが大事だと思っています。

(https://www.yokosuka-clinic.com/)
正しい情報を提供し、将来の選択肢を狭めない
―診療時に心がけていることや、工夫されていることはありますか
まず大切にしているのは、「患者さんの希望を尊重すること」です。どんな治療が適しているのかを、医師が一方的に決めるのではなく、「患者さんがどうありたいか」「何を優先したいのか」を丁寧に伺いながら、一緒に選んでいくことを心がけています。
婦人科の診療は、患者さん一人ひとりのライフスタイルや価値観に深く関わる分野です。「月経時のつらい症状を軽減したい」「PMSを何とかしたい」といった明確な目的のほかに、「肌の調子が気になる」「避妊を考えたい」といった複数の希望をお持ちの方もいらっしゃいます。なかには「費用を抑えたい」「毎日薬を飲むのは大変」といったご事情がある方もいて、背景や優先順位は本当にさまざまです。
ですから、まずは問診や会話を通じて、その方の希望や思いをできる限り正確に把握することが第一歩です。そのうえで、ピルなどの選択肢の中から続けやすく、生活の質が上がるものをご提案しています。薬を「一方的に処方されるもの」ではなく、「自分で選んだもの」として納得して使っていただくことが継続につながると考えています。
そうした選択をしていただくためには、やはり“正しい情報提供”が重要です。
たとえば、今のご自身の体の状態 −排卵の有無や婦人科系疾患、筋腫やポリープの有無など、採血検査や内診・超音波検査を通して丁寧に説明しています。また、お薬の効果だけでなく、副作用やリスクについても必ずお話ししています。
「この薬を使うと生理が楽になりますが、最初の2〜3ヶ月は不正出血があるかもしれません」「血栓症のリスクもゼロではないので、もしこんな症状が出たらすぐに連絡してくださいね」など、良い点と注意点の両方をお伝えし、見通しを持って治療を始めていただけるようにしています。
私が婦人科医として大切にしているのは、「将来の選択肢を狭めないこと」、そして「その方らしく、楽しく生きるお手伝いをすること」です。方法にこだわるのではなく、患者さんが自分らしくいられる選択を後押しできる医療を提供していきたいと思っています。

―先の見通しを知ることは治療を継続する上で大事ですよね。患者さんお一人おひとりを丁寧に診ていく工夫は何かあるのでしょうか
患者さんのお困りごとや希望を把握する上で、問診には十分な時間をかける必要があり、そこはスタッフの力がとても大きな支えになっています。
初診の患者さんなど、まずはスタッフが話を聞くことで、リラックスして話やすいよう工夫しています。当院のスタッフはとても優秀であることに加え、患者さんのお気持ちに寄り添える優しいスタッフばかりなので、問診の段階から患者さんの気持ちを丁寧にくみ取り、必要な情報を私に伝えてくれますし、ときには「この方にはこの薬が良さそうですね」と患者さんと相談して方向性を共有してくれることもあります。
スタッフ同士もとても仲が良く、最初こそ少し指導もしましたが、今ではお互いに教え合いながら自然とチームワークができています。基本的にはスタッフの意見を尊重して進めることで、うまくいくと実感しています。
私は医師として、治療開始直後のサポート、再診の時の診察に時間をかけるようにしています。ホルモン治療は、安定するまでに3〜6ヶ月かかることがあります。出血や痛み、体調の変化など、患者さんが不安を感じやすい時期に、医師が直接しっかり関わることが重要だと考えています。問診だけでなく、根拠を持って方針を決定したりご説明したりすることが必要と考えていますので、症状のある時には検査を必ず行っています。
また、待ち時間の短縮や来院の負担軽減につながる工夫もあります。定期的なお薬の処方など、すでに安定している方を対象に「オンライン診療」や、「すぐ枠」という20分以内の短時間枠を設けています。「すぐ枠」は対面診療ではありますが、あらかじめタブレットで問診を記入していただき、20分以内で“すぐ”に処方できるという仕組みです。
もちろん必要なタイミングや症状があった際には時間をかけて問診したり、内診や超音波検査・採血検査をおこなったりしています。 実際、以前よりも「待ち時間が長い」といった声は少なくなってきた印象です。スタッフと一緒に「このやり方はどうだろう?」と話し合いながら、改善を積み重ねていけるのが、開業の醍醐味だと感じています。

いつまでもごきげんに過ごせるための基盤づくりを共に考える
―産婦人科医としてのやりがいを教えてください
私が日々やりがいを感じているのは、患者さんの人生に長く寄り添いながら、その変化を一緒に見届けられることです。
たとえば、生理のつらさで受診された方が、ホルモン治療で体調が整い、「彼氏ができました」と話してくださることがあります。そこから「子宮頸がんワクチンを受けたい」といった前向きな行動に繋がることも。その後、「結婚しました」「妊活を始めたいです」とライフステージごとに相談を受け、ホルモン治療を中止しブライダルチェックの直後にスムーズに妊娠される…そんな流れを気持ちを同じくする大切なスタッフと見守れることに、大きなやりがいを感じています。そんな経過を経てご出産された患者さんが、お子さんを連れてきてくださることもあるのですが、毎回感激し泣きそうになっています!
ホルモン治療を導入する際、私の中では「妊娠しづらい体にならないようにする」という視点をとても大切にしています。もちろん妊娠・出産を選ばない人生もありますが、自分で「産まない」と決めるのと、「産みたいけど産めない」というのとでは意味合いが大きく異なります。「子どもを産みたい」と思ったときにその選択肢を残しておけることは、とても重要だと考えています。
私自身、日々の診療の中で大切にしている3つの柱があります。
- まずは毎日を快適に過ごし、自分の人生をプランニングする
- プレコンセプションケアで将来の妊娠に向けたボディメンテナンスをする
- 100歳をこえても、ごきげんにすごせる基盤作りをする
こうした視点でライフステージ全体を見ながら、患者さんと一緒にプランを立てていくことが、私の仕事のやりがいにつながっています。


生理を“コントロール”して 自分の身体と生活を守る
―先生ご自身も月経にまつわる不調をご経験されたと伺いました。不調との向き合い方をお話しいただけますか
生理は「あるのが当たり前」「つらいのも仕方ない」と思われがちですが、実はコントロールが可能です。生理を無理に我慢したり、毎月つらい思いをしたりする必要はありません。適切な治療で症状を改善し、生活の質を高めることができるのです。
私自身、PMS(月経前症候群)がかなり重く、特にPMDD(月経前不快気分障害)が強く症状として出ていて、周囲からは「精神科に行ってみたらどうか?」と言われることもありました。実際にPMDDには精神科で使われるSSRI(抗うつ薬の一種)の効果があるとされています。
私の場合、婦人科で処方されるホルモン療法、ピルもそうなのですが、特にジエノゲスト(黄体ホルモン剤)という薬に助けられました。
月経困難症やPMSの治療にピルを使うことはよく知られていると思います。ピルとひとことで言っても、保険適用のものや自費のもの、価格も成分もさまざまです。ピルの副作用でつらい思いをされた方もいらっしゃるかもしれません。
ジエノゲストには血栓症の副作用がなく、初経から閉経まで幅広い年代の女性に適応があります。「知っていて選ばない」のと「知らなくて選べない」のとでは、まったく意味が違います。
当院では、ホルモン治療の選択肢としてジエノゲストを提案しています。
▶︎ ジエノゲスト(新提案・ピルとは別の保険ホルモン治療):https://www.yokosuka-clinic.com/dienogest
―「我慢する」から「コントロールする」に意識を変えるというのも大切ですよね
そうですね。生理は当たり前だから我慢しなきゃ、という考えから、「自分の体と生活を守るためにコントロールしていいんだ」という発想がもっと広まってほしいです。生理に振り回されるのではなく、自分で生理をコントロールして人生をよりよくしていく。そうした選択肢を持つことが女性の自信にもつながると思います。
ホルモン療法は、もちろん合う合わないはありますが、正しく使えば人生を前向きに過ごすための強力なツールです。女性が自分らしく強く生きていく象徴だと私は考えています。
今、企業の中でも「生理休暇」という仕組みや制度が広がりつつありますよね。つらい時に休みやすいという環境づくりは重要です。ただ、不調で休むということは、皆と同じように働けないということです。私は、生理のつらさは薬で軽減して、皆と同じように働けることに価値があると感じています。
一人に与えられる「時間」は平等で本当に貴重です。ご自身の体調や生活を自分でコントロールして、仕事もプライベートもより充実させてほしいと思います。
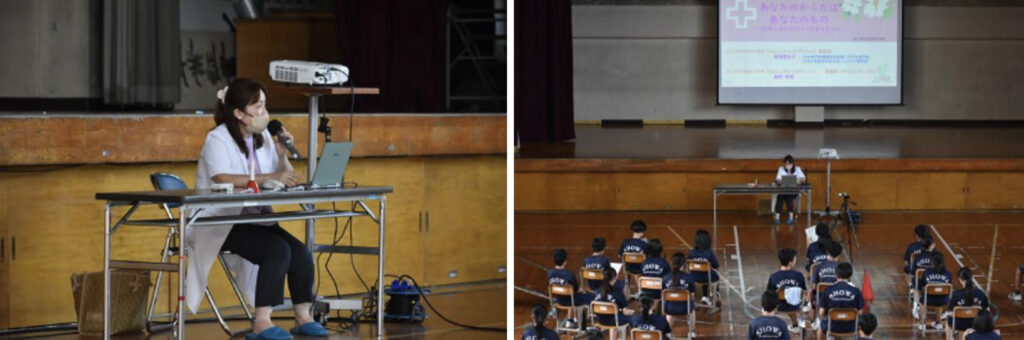
「相談してみようかな」、その気持ちを大切に
―読者へのメッセージをお願いします
生理やPMSのことで悩んでいる方には、ぜひ気軽に婦人科に相談してほしいと思っています。
もし最初に受診した医療機関で「何となく合わないな」と感じた場合は、どうか無理をせず、他の病院に足を運んでみてください。婦人科は相性もとても大切です。お医者さんとの関係だけでなく、看護師さんやスタッフの方々とのやりとりの中で「ここなら話せるかも」と思える場所に出会えることもあると思います。
私自身、学生の頃に婦人科にかかったときは、なかなか自分に合う場所を見つけられず、通院が続かなかった経験があります。特に若い頃は診察そのものに戸惑いや緊張もありますし、大人になってからでも、うまく伝えられないまま診察が終わってしまうこともあるかもしれません。
それでも、「話を聞いてもらえた」と感じられる経験は、きっと大きな支えになるはずです。不安な気持ちを抱えたまま我慢せず、どこかに話を聞いてくれる人は必ずいます。どうかひとりで抱え込まずに、「相談してみようかな」と思えたその気持ちを大切に、一歩踏み出してみてくださいね。

朝のジョギングで健康管理とリフレッシュ
ー先生のリフレッシュ方法を教えてください
私にとって一番のリフレッシュ方法は朝のジョギングです。毎日4時頃に起きて仕事や家事をした後、30分から1時間ほど走っています。冬はまだ真っ暗で寒いですが、外に出て走り始めると不思議と気持ちが切り替わります。雨の日はジムで体を動かすようにしています。
走ると頭がすっきりしますし、体調の変化にも気づきやすくなるので健康管理にもなっています。私自身、ホルモン治療の副作用による更年期症状を経験したことがあるのですが運動によってかなり楽になることを実感しています。太陽の光を浴びることは骨の健康にも良いですし、心と体の両方にとって欠かせないリフレッシュの時間になっています。
飼っている猫たちと過ごす時間や犬の散歩も大きな癒しです!走ってリフレッシュして、猫や犬に癒されて…そんな毎日が、私の元気の源です。
(取材:2025年5月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。