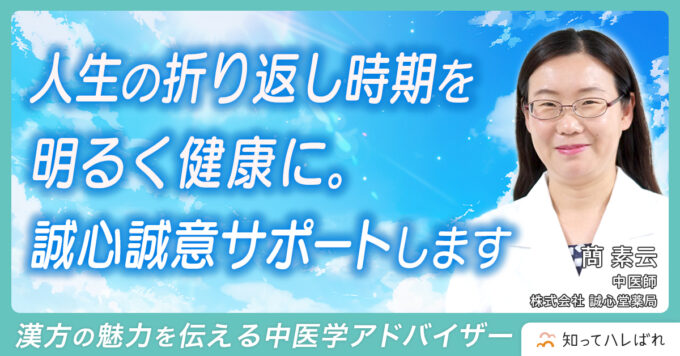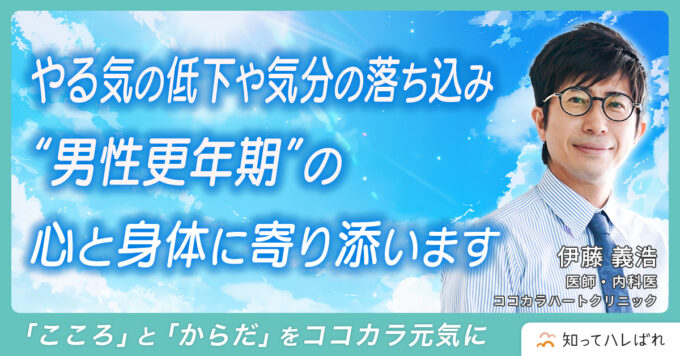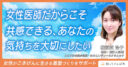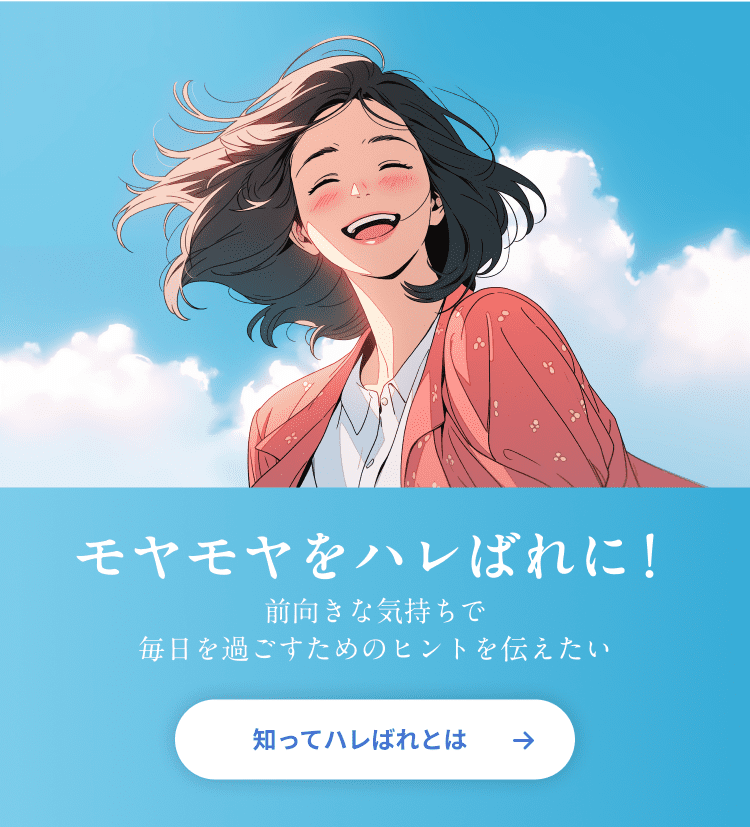ご自身の可能性を信じることで道は開ける 選択肢を狭めず一歩を大切に【医師 高橋 敬一】
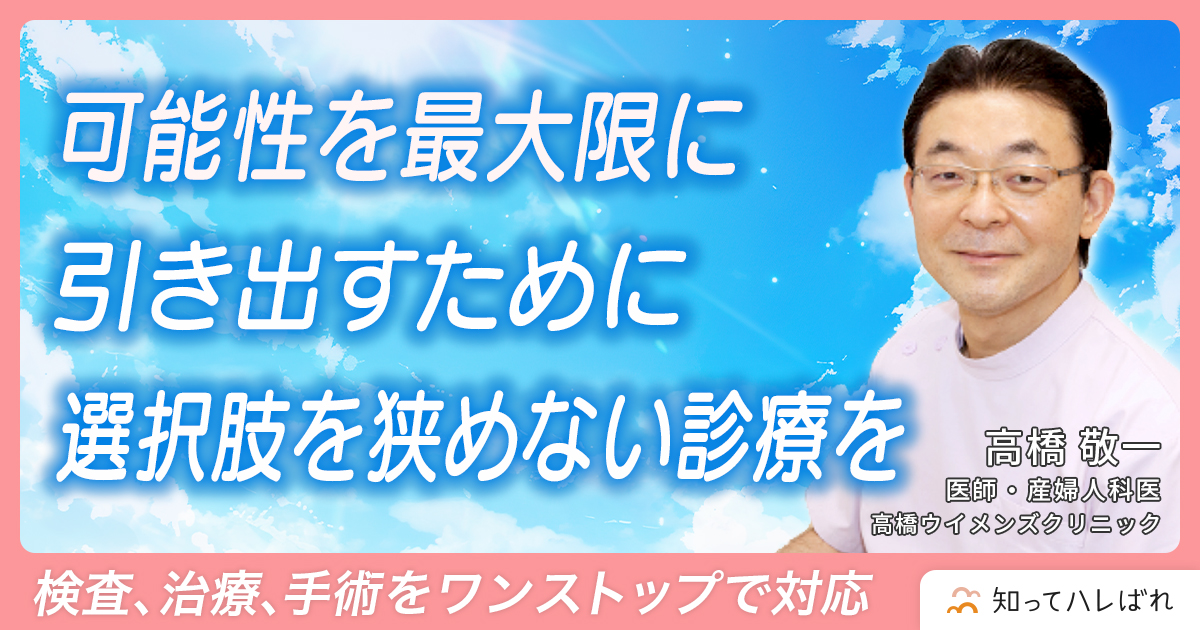
目次
「創造する」医療への興味から生殖医療の道へ
――産婦人科医を志したきっかけを教えてください
今から40年以上前のことなので、今思うと少し青臭くて恥ずかしいのですが、当時は社会の歪みに関わることに関心がありました。特に女性の問題や精神疾患を抱える方の課題は、社会問題が色濃く表れる分野だと感じていましたね。当時は、今ほど女性の社会的地位が高くなかったこともあり、社会的に弱い立場にある方々と関わりたいという思いが強く、「精神科」か「産婦人科」に進みたいと考えていました。
結果として産婦人科を選びましたが、学生時代には精神科での実習経験しかなく、お産を一度も見ずに産婦人科医になったという、かなり珍しいケースだったと思います。研修医として最初に勤務した病院で、「お産を一度も見たことがない」と正直に話したときは、周囲が驚いてその場の空気が凍りついたのを今でも覚えています。
もともと私は、何かを「つくり出す」ことが好きでした。小さい頃から農家の環境で育ち、豚や牛、猫のお産を間近で見てきましたし、自分で鶏小屋を作って卵を孵化させるなど、生命の誕生に関わる体験も多くありました。そのような背景から、「生命」への関心は自然に育まれていたのかもしれません。
――産婦人科医としてスタートして、「生殖医療」の道へと進まれた経緯をお聞かせください
生殖医療は、“創造する”医療だと思っています。他の診療科が「治すこと」、つまり修復やリペアを目的としているのに対して、産婦人科、特に生殖医療は「新しい命の創造」に関わることができるという点に大きな魅力を感じました。
私が大学を卒業した頃は、ちょうど日本で初めて体外受精による赤ちゃんが誕生した時期でもあり、「体外受精」という技術自体が始まりを迎えた時代でした。
産婦人科医として病院勤務の中で、お産やがん治療など幅広い研修を積ませていただきましたが、新しいものが好きな性格もあり、最先端の分野である生殖医療を学びたいという思いが徐々に大きくなったのが今に続くきっかけですね。
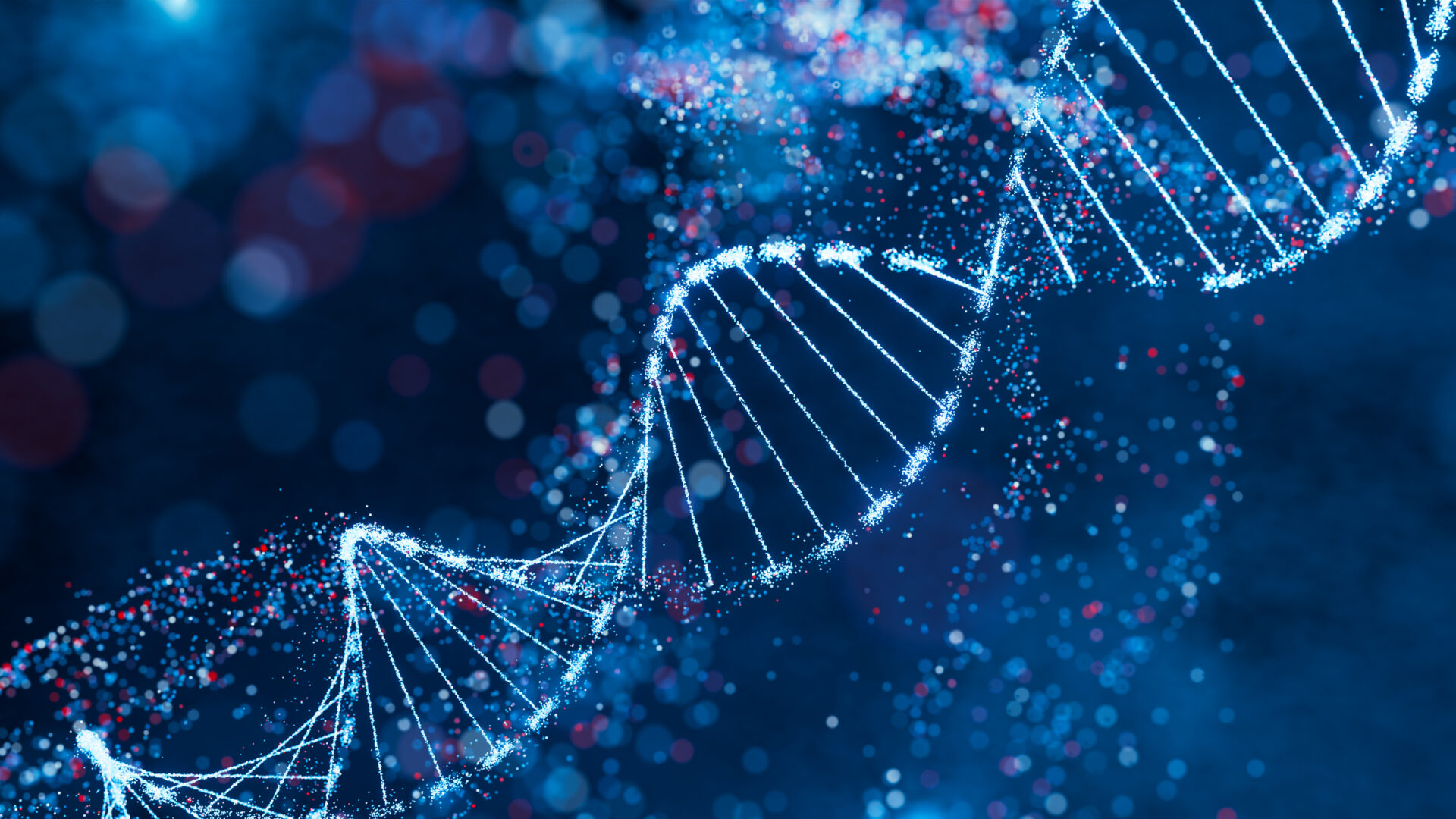
――開業を決意されたのはどのような経緯があったのでしょうか
生殖医療に携わり始めた当時、私が勤務していた虎の門病院は、生殖医療の分野でも最先端の環境が整っている場所でした。ただ、どんなに最先端でも、5年10年と経つうちに状況は変わってきます。生殖医療に携わる先生方は、開業されている方も、大学にいる方も、みなさんその分野に専念しているのですね。
一方で、虎の門病院は総合病院です。不妊治療に携わりながら、お産も担当し、がんの患者さんも診る必要がありました。もちろん、お産も好きでしたし、やりがいのある仕事です。最初はそれでも何とかやれていましたが、すべてをトップレベルで続けていくのは難しいと次第に感じるようになりました。
たとえば採卵の最中に「赤ちゃんの心拍が落ちています」と呼ばれれば、すぐに駆けつけなければならない。また、3〜4時間のがん手術の後に卵子を扱うことは、心身ともに限界に近づいてしまいます。
昔は「何でもできる医師」が一つの理想とされていましたが、今は専門性の高い分野で先端を走り続けるには、一つの分野に絞って取り組む必要があると痛感しました。実際、周囲の先生方と比べて、自分の診療のアップデートや学びにかけられる時間に差が出てきて、自分が納得できる医療を提供するためにも、選択と集中が必要だと感じたんです。
最終的には「どちらを選ぶか」という判断になり、私は不妊治療を専門にする道を選びました。この分野は日々進歩していて、学びが尽きないのも魅力の一つですし、それが楽しくもあります。 そうした経緯から、専門に集中できる環境を自分でつくるために、開業を決意しました。

(https://www.takahashi-w-clinic.jp/)
可能性を最大限に引き出すために選択肢を狭めない
――診療で心がけていること、意識していることを教えてください
自分のスタイルとして意識しているのは、やはり“バランス”です。
私自身、昔からひとつの分野に特化するというよりも、全体を見渡しながらオールマイティーに診療してきたタイプです。自分で言うのも少し恥ずかしいんですが、いろんなことを平均的にこなす、いわゆる“バランス型”だと思っています。
不妊治療の分野では、体外受精の第一世代にあたる年代なんですが、私は手術も好きで得意だったので、体外受精一辺倒ではなく、腹腔鏡や内視鏡の手術なども多く担当してきました。アメリカに留学した際は、クラミジア感染による卵管癒着の研究をしていたこともあり、卵管に関する知見や手術にも強い関心がありました。そのような背景もあり、不妊症だけでなく手術も含めて幅広く診てきた経験があります。
現在のクリニックも「不妊症専門」ではありますが、「体外受精専門」ではありません。体外受精に特化している施設もありますが、私はあえてそこにこだわらず、患者さん一人ひとりに合わせた治療法の選択肢を広く持つことを大切にしています。
体外受精は確かに成功率が高い治療法ですが、それが必ずしもすべての方にとって最適とは限りません。タイミング法や人工授精なども含め、幅広い可能性を考慮したうえで、その方にとってベストな選択ができるように心がけています。
要するに、「治療法に人を当てはめる」のではなく、その人の可能性を最大限に引き出すために、選択肢を狭めない診療をしたいと考えています。患者さんの背景や状況を踏まえて、「この方には何が一番可能性が高いのか」を常に考えながら、治療の方向性を一緒に決めていく。そういった姿勢が、私なりの診療の軸になっていると思います。

――医師としてのやりがいを教えてください
やはり一番のやりがいは、患者さんが妊娠されたときですね。「よかったですね」と一緒に喜べるのは、私にとっても本当に嬉しい瞬間です。
特に印象的なのは、42歳の女性が初めてのお子さんを授かったケースです。赤ちゃんとご夫婦と、そしてご夫婦それぞれのご両親とともに7人で写った病室での家族写真を送ってくださったのです。ご両親はもう70歳ごろで、おそらくご夫婦もそれぞれの親御さんも最後のチャンスだと思ってらしたことでしょう。その写真の中には、赤ちゃんを囲んで微笑む6人のご家族の姿があって、「ああ、この子は本当に宝物なんだなあ」と、胸が熱くなりました。
この子には、ご両親やご祖父母の思いがすべて繋がっていて、自分はその瞬間に関わる事ができたのだと思うと、医師としての存在意義というか、「自分がこの仕事をしている意味」を改めて実感します。
私は開業してこれまでに2万人以上の妊娠に関わってきました。おそらく日本武道館がいっぱいになるくらいの命の誕生に関わってきたわけで、それは本当にすごいことだなと思いますし、自分の歩んできた開業25年間の重みを感じます。
「生活が変わりました」だけではなく、「人生が変わりました」とおっしゃってくださる方もいらして、そのような言葉をいただくと、この仕事をしていて本当によかったと心から感じます。こうして自分の仕事を通じて、人の人生に深く関わりながら、その人たちの未来をつくるお手伝いができているというのは、医師として、そして一人の人間としてとても幸せなことだと思っています。


「栄養不足=材料不足」、タンパク質と筋肉に注目
――最近、女性の「タンパク質不足」「筋肉不足」、いわゆる痩せの問題が話題に上がることがありますが、診察の現場で感じていらっしゃることはありますか
そうですね。以前は卵の質が良くない方というと、主に肥満の方が多く、妊娠率が低くなる傾向があると考えられていました。ただ、ここ数年の診療の中で、それとは少し違う印象を持つようになりました。体重は標準的で、しかも若い方なのに、なぜか卵の質が良くないというケースが増えてきたと感じています。
その中で、特に痩せ型の方や、いわゆる“かくれ肥満”と言われるような体型の方に、卵の状態が良くないケースが多く見られます。そこから気づいたのが、「タンパク質」と「筋肉」が不足しているということです。
痩せている方やかくれ肥満の方の問題は、やはり栄養不足によるタンパク質不足と筋肉量の少なさで、結果として体調を崩しやすくなっている印象があります。これは「やせすぎ」としてメディアなどでも特集されていましたが、私の臨床の実感とも一致します。
血液検査をしてみると、痩せている方はタンパク質やコレステロールの値が非常に低いことがわかりました。
――コレステロールは“低い方がいい”と思っていましたがそうではないのですか
一般的には「コレステロールが低いのは良いこと」と思われがちですが、実際にはコレステロールも重要な栄養素です。もちろん、高すぎると心筋梗塞のリスクなどもあるため注意が必要ですが、低すぎても問題です。
ただ、コレステロール値が基準値をかなり下回っていても、健康診断では問題なしの「A判定」が出てしまうことが多く、問題に気づきにくいという現実があります。
そもそも細胞膜は「リン脂質」と「コレステロール」で構成されています。また、性ホルモン(男性ホルモンや女性ホルモン)も、中核となる構造はコレステロールからできています。そのため、コレステロールやリン脂質が不足しているというのは、ホルモンや細胞そのものの材料が足りていないということになるわけです。
いま私が一番注目しているのは、まさにこの「栄養不足=材料不足」、そして「血液循環・血流の悪さ」という部分です。
現在の日本人女性の中には、栄養不足の方が非常に多いという印象を持っています。痩せ型の方はもちろんですが、見た目が普通の体型の方でも、体組成計で調べてみると、筋肉量が少なく体脂肪率が高い“かくれ肥満”の方が多くいらっしゃいます。
筋肉が少ない方は当然ながら体をあまり動かしていません。すると血流も悪く、冷え性もひどい方が多いのです。そしてこれは、子宮や卵巣の血流も悪くなるということです。
結果的に、タンパク質やコレステロールが足りない、筋肉がない、血流も悪い――という状態では、良い卵は育ちません。そのような方にはまず「しっかりタンパク質を摂ってください」「筋肉をつけてください」とお伝えしています。
不妊治療における「目指す状態」は「病気でない生活」とは異なります。「病気でなければOK」ではなく、不妊治療では「妊娠して、お子さんを健康に胎内で育てて、出産を目指す」わけです。つまり、「理想的な健康な状態」を追求する必要があるのです。
筋力をつける、といっても散歩やウォーキング程度では正直足りません。意識して筋トレするくらいじゃないと、理想的な筋肉はなかなかつきません。ウォーキングをするにしても、ダンベルを持って早歩きくらいの強度が必要です。
最近では「着床障害(着床不全)」が注目されてきていますが、実際には「着床するかしないか」は7割が卵の質で決まります。着床不全に関しては、医師が検査や治療をおこなうためご本人にできることは少ないですが、卵の質を良くする努力はご自身でできます。「いい卵を作る」という観点からも、自分でできる基本の生活を見直すことがとても重要だとお伝えしています。

選択肢を狭めず、ご自身の力を信じてください
――読者へのメッセージをお願いします
「ご自身で可能性を狭めすぎないでください」とお伝えしたいです。
私のクリニックでは、できるだけ多くの選択肢を提示できるようにという方針で治療を進めていますが、中には「もうこれしかない」と自ら選択肢を絞り込んでしまう方もいらっしゃいます。
たとえば、体外受精をされている方の中には、「もう体外受精をしているから、タイミング法や人工授精は無駄」と、それ以外の手段をすべて無意味に感じてしまうケースもあります。でも、それは本当にもったいないことだと思います。
もちろん、体外受精を主軸に治療を進めること自体を否定するつもりはまったくありません。ただ、それと同時に、他の可能性までご自身で閉ざしてしまう必要はないのです。実際に、体外受精でうまくいかずに、人工授精や自然妊娠によって妊娠に至る方もいらっしゃるのですね。
大切なのは、ご自身の可能性を信じて、少しでも望みのある方法があるのであれば、無理のない範囲で取り入れてみる姿勢ではないかと思います。どうか、自分たちの力を信じて、焦らず一歩ずつ取り組んでほしいと願っています。

仕事をできない環境に身を置いてリフレッシュ
――最後に、先生ご自身のリフレッシュ方法を教えてください
私の場合、ありがたいことに仕事そのものが大きな喜びになっています。患者さんが妊娠されるという結果が本当にうれしくて、それが自分の原動力になっているのです。ですから、いわゆる“リフレッシュ”とか“リセット”といったことを意識する機会は、仕事がうまく運ばなかった時ぐらいでしょうか。
あえてリフレッシュを挙げるとすれば「旅行」です。仕事中はつい集中しすぎて没頭してしまうので、完全にそこから離れるには旅行が一番です。旅先では、何かあってもすぐには対応できませんし、ある意味で「何もしない」ことが許される、そういう環境に身を置くことで、気持ちをリフレッシュして、また新鮮な気持ちで仕事にもどれているように思います。
それから、私はやはり「目に見える成果」があると気持ちが高揚しますので、皆さまの妊娠と出産報告が、自然とリフレッシュになっているのかもしれません。
(取材:2025年4月)
本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。