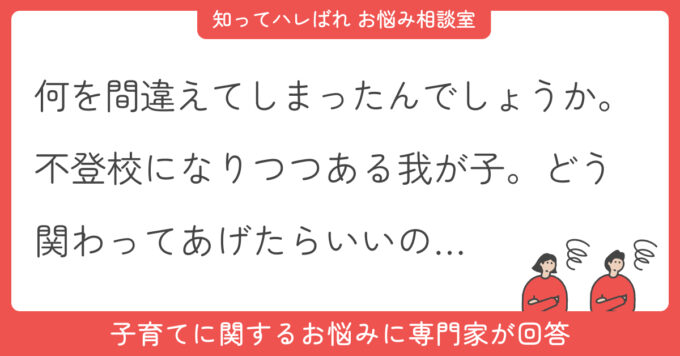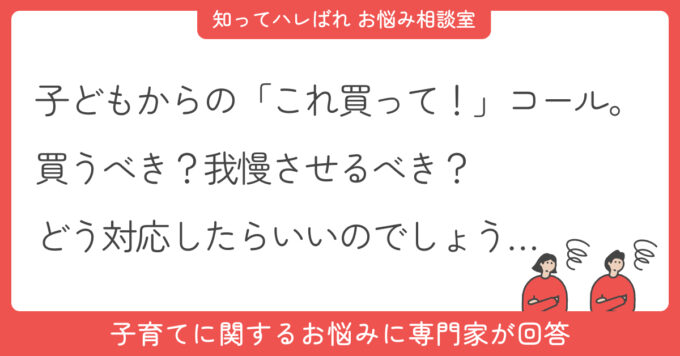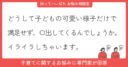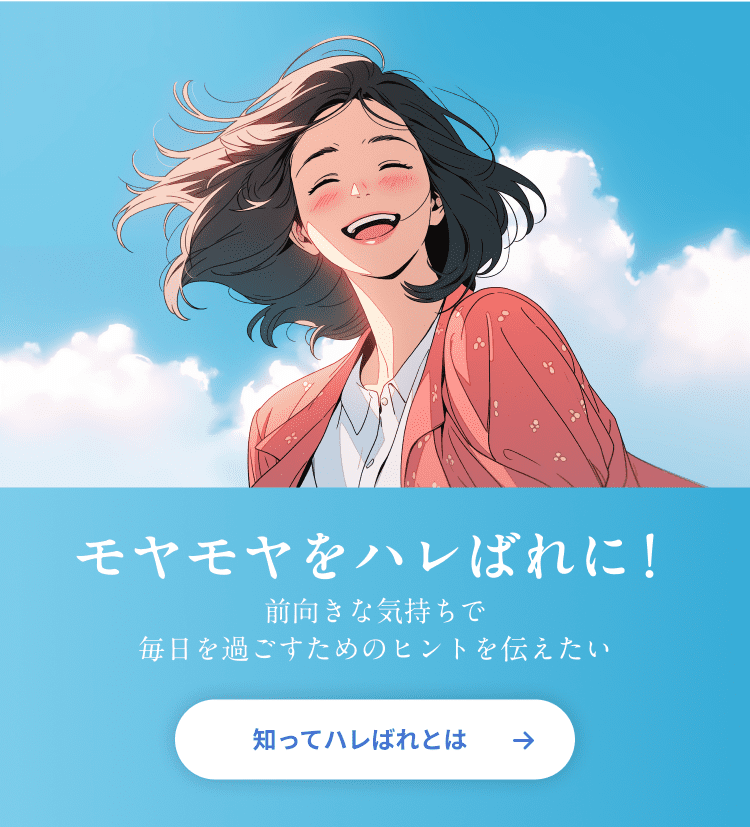実体験を活かして多くの親子をサポート。親子関係の立て直しに遅すぎることはありません【医師 鈴木 裕美】
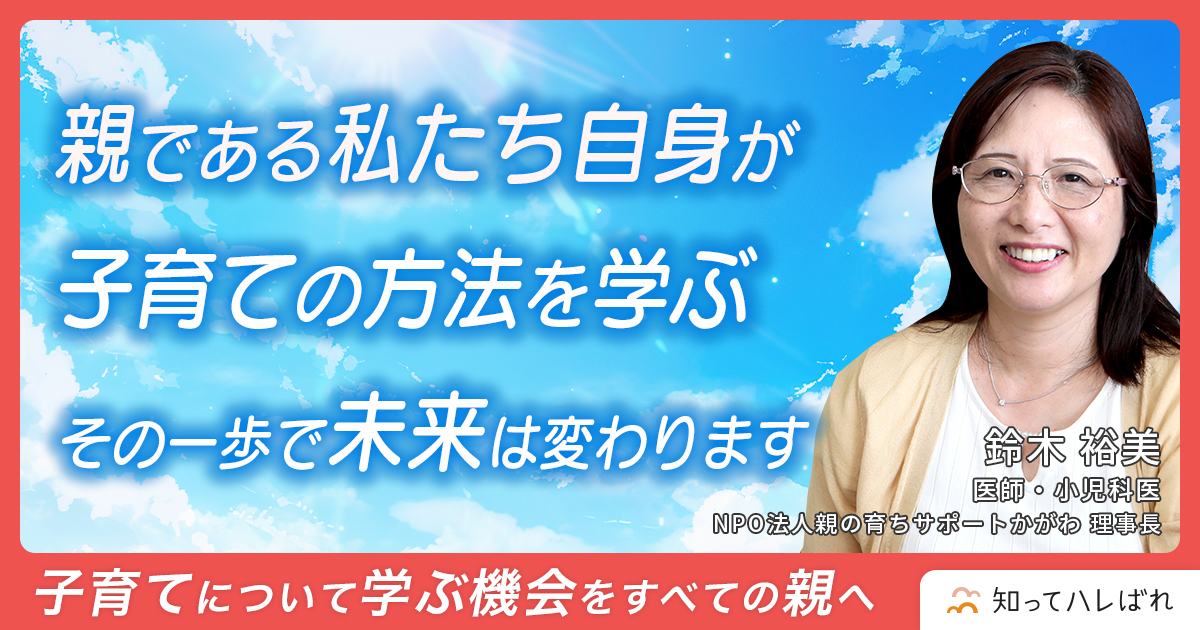
目次
働きたいけど働けない。3人の子どもを育てながら、34歳で医学部に挑戦
ー鈴木先生のこれまでのご経歴を教えてください
小さな頃から海外に興味関心があって、中学生の頃にアフリカのテレビドキュメンタリーを見て「子どもたちを助けたい」「海外で働きたい」という思いをずっと持っていました。
大学では国際関係を専攻していて、太平洋諸島に興味を持ち、休学してミクロネシアの島々を旅してまわりました。一旦は帰国しましたが、もっと太平洋諸島のことを学びたいと思い、大学を中退してハワイ大学に編入。卒業後は大学院で公衆衛生学の国際保健を専攻し、ユニセフやWHO(世界保健機関)などの国連機関で働きたいと考えていました。
学生時代に夫と出会い、学生結婚そして出産をしましたが夢をかなえるために勉強を続けていました。

ー海外で学びながら、学生結婚、さらに子育てをしながら学び続けるなんて、すごいです
実際は、就職をしたかったのに出産のためにチャンスを逃しているんです。
1人目が生まれたときは、学んできた公衆衛生の知識を活かしてハワイ州の行政で働くつもりだったのですが、妊娠出産育児のため諦めざるを得ませんでした。
2人目が生まれたときは、夫の仕事の都合でブラジルに住んでいました。
ちょうどその頃、3回受験した国連の試験に受かって、家族4人で大枚をはたいてスイスまで最終の面接試験に行ったのですが結果は不合格でした。その後、3人目を授かったことが分かり、国連で働く夢をあきらめました。
「社会に貢献したい」という思いから大学院にも行ったのに、専業主婦をしているという現実に直面し、自分の今までの努力が無になる気がして、当時は悶々としていましたね。「こんなはずじゃなかった」という思いはずっとありました。
ー日本に帰国されてからお医者さんを目指されたのはどのようなきっかけがあったのでしょうか
帰国してから3人目を出産して、毎日子育てに追われていました。
子どもはもちろんかわいいのですが、キャリアがスタートできないというモヤモヤとした思いをずっと抱えて、相変わらず悶々としていましたね。
同居していた母に「まだ若いんだから、国家資格でも取って働いてみたら?」と言われたのがきっかけで進学を意識するようになり、偶然にも医学部の学士編入の新聞記事を見つけました。理数系が苦手だったので医学部はハードルが高いと思っていましたが、編入であればもしかしたら私でも合格できるのではないかと思い、医学部を目指すことにしました。

医学部の受験を決意したのが34歳で、合格したのは37歳の時です。3年かけて入学を果たしました。
「その年齢でよくやる気になったね」と言われますが、それまで何もできていなかった反動だと思っています。あとは、失うものが何もなかったんです。もしダメだったとしても「主婦」とか「母」という肩書きは残るじゃないですか。だから合否の結果で私は何も変わらないから、「とにかくやってみよう」という気持ちでチャレンジしました。
「女性である」がためにできないことも多かったけど、「女性だからできる」ということもあったので、私は女性でよかったんだ、と思うようになりました。
ー医学部に進学されて小児科医を目指されたのはなぜですか
公衆衛生を学んでいたことや、海外の暮らしが長かったこともあり、ストリートチルドレンやエイズ孤児を目の当たりにしてきて、子どものために何かできることをしたいっていう思いはずっと持っていたんですよね。
ただ実際に小児科医をやってみて、自分は向いていないと感じることもありました。
大学病院の小児科病棟に来るお子さんは、難しい病気であることが多いですし、治療も厳密さや緻密さが必要です。
お薬も体重によって緻密に計算する必要がありますし、点滴をするにも髪の毛くらい細い血管の赤ちゃんもいるので、大人よりもずっと手技も難しいんですよね。もともと大雑把で不器用な私は向いていないと思うことがありました。
あとは小児科医とは直接は関係ないのですが、年齢的、体力的な問題です。当直が続くと30時間以上の連続勤務もあり、普段はミスしないようなミスをしてしまったり。
家庭や子育てとの両立も難しいなと感じていました。子どもが思春期なのに話を聞いてあげられない、子どもが体調を崩していても仕事に行かなければいけない。「何のために働いてるのかな」という気持ちになることもありました。
そんな時たまたま公衆衛生の教授から声をかけていただき、病棟勤務を外れ公衆衛生の研究室に入りました。
不登校や生きづらさ、子育ての方法がわからない 私たち親子と同じ悩みを抱えている方たちを救いたい
ー現在は「NPO法人 親の育ちサポートかがわ」で子育て支援に取り組まれていらっしゃいますが、お取り組みについて教えてください
「親の育ちサポートかがわ」は、“すべての親に子育てについて学ぶ機会を提供する”ことをミッションに、 情報発信やワークショップ、子育てに悩みを持つ親への情報提供やケアを行っています。
最近では、フリースペース開設や当事者や保護者が交流できる仕組みづくりや情報発信など、不登校や生きづらさを抱える子どもをサポートする活動もしています。

NPO法人 親の育ちサポートかがわ
https://www.oyanosodachi-support.com
ーお取り組みを始めるきっかけはなにかあったのでしょうか
私自身の母親として、そして小児科医として得た知識や経験を生かし、子どもに関わる人たちの力になりたいと考えたからですね。
自分自身もそうでしたが、親になっても実はどのように子どもに接していいか知らない、適切な子育ての方法がわからない人は多いのです。
私には3人の子がいますが、長女は第1子ということもあり厳しく育ててしまい高校を卒業するまで適切なコミュニケーションが取れていない状態でした。末っ子は長女の時の反省を活かしうまくできていると思っていたのに、うつ病になって通学できなくなり高校を中退してしまいました。
子ども側に問題があると思っていましたが、自分自身が子育てについて学んでいくうちに、実は私側に問題があったことに気づきました。
子育てについて学ぶと、子どもに適切な態度で適切な言葉かけをすることができます。自分の経験を活かして同じ悩みを抱える親子の力になりたいという想いで活動しています。
なにより親子関係の立て直しに遅すぎることはない、今からでも間に合う!ということを伝えていきたいのです。
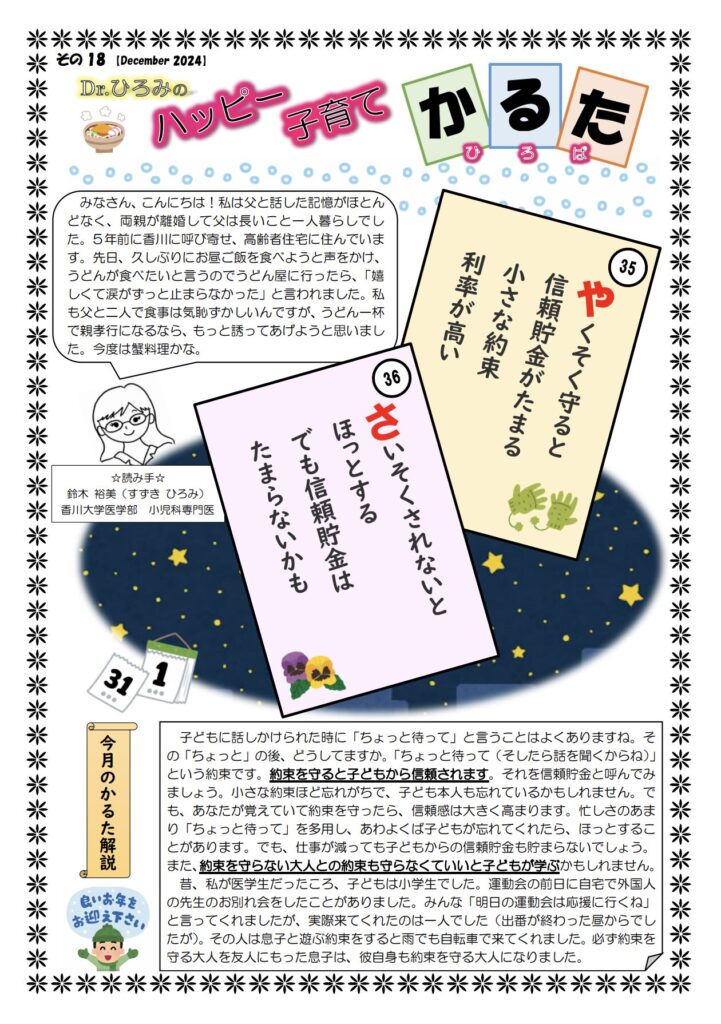
親子関係の立て直しに遅すぎることはない!
ー「親子関係の立て直しに遅すぎることはない」という言葉はとても心強いです。先生ご自身の子育てエピソードを教えてください
長女の時は、私自身が働きたいのに働けないと悶々としている時期で、子育てを楽しめずイライラしてしまい、厳しく接してしまうことも多くありました。私が厳しくしたり怒ってばかりだから、娘も反発するといった悪循環が続き、中学生や高校生になってもお互いに会話もほとんどしていませんでした。
長女の気持ちに気付いたのは、彼女が高校を卒業するタイミングでした。
卒業の時、他のみんなは保護者に感謝の手紙を渡していましたが、自分の娘から手紙はもらえませんでした。後になってその手紙を自宅で見つけ、「自分はこの18年間、家に居場所がなかった。お母さんは弟妹をすごく可愛がって、自分だけすごく辛かった。お母さんのあの時の言葉がこんな風な気持ちで辛かった」という内容と、最後に「ママなんて大嫌い」と書いてあったんです。
最初は誤解されていると腹が立ちましたが、徐々に18年も「自分に居場所がない」とか「愛してもらえてない」という思いを抱えて辛かっただろうな、この手紙を渡せなかった気持ちを思うと私もとても切ない気持ちになりました。
それからは、娘を否定することをやめて前向きな言葉だけをかけることに決めました。
彼女のいいところや頑張っているところを見つけて言葉にしたり、励ましたり、できるだけ前向きな言葉をかけるようにしました。手をつないだり、一緒に寝たり、一緒にお風呂に入るなど、子どもの頃に十分できなかったことをもう1回なぞるっていうんですかね。「愛してほしい・見てほしい・認めてほしい」の気持ちを満たせるよう、一緒に楽しい時間を過ごすように努めました。
そうするうちに長女はみるみるうちにすごく変わっていきました。友達もどんどん増え、大学での勉強に前向きに取り組み、資格試験に挑戦したり、ボランティア活動を始めたり。別人のようにアクティブになってどんどん明るくなりました。
長女と向き合い始めたのは、彼女が19歳の時でしたが、「こうやって親子の関係は作り直せるんだ」と実感できました。
逆に下の子にはずっと前向きな言葉がけをして、いい関係値を築けていると思っていたのですが、彼女自身ががんばりすぎてうつ病、不登校になってしまいました。「過剰適応」と言って、自分を後回しにしてでも周りを喜ばせるため、期待に応えるために、と頑張りすぎちゃうんですよね。不登校のお子さんに多いタイプです。
親の接し方やその子のパーソナリティ、周囲の環境がかけ合わさって、問題が大きくなったり、長引いたりしますし、一概にこれをやれば大丈夫、やらないからダメとはならないので、子育てって本当に難しいですよね。

子どもも大人も活躍の場はひとつだけではない
ーお話を伺っていると「働けない」とか「向いていない」「子育てに悩んだ」という状況をネガティブなまま終わらせず、次の経験につなげていらっしゃるなと感じています
そうですね、どんな経験でも無駄なものはないと思っています。
先のことをあんまり考えずにやってきていますが、その時にやりたいことをやる、突き動かされたものに従ってやっているといつの間にかうまく進んでいくっていう感じです。もちろん強い想いは持っていて、その時はもう全力で一生懸命やっています。
それでも「うまくいかないな」「向いていないな」と思う時は、きっと今やっていることを辞めて、次のステージに行くように導かれているんだろうなと思っています。神様がそう言ってるみたいな、特に何か信仰してるとかではないですよ(笑)。
国連の試験に落ちた時も、「今は仕事をしたいと考える時ではなくて、子育てに集中しなさい」って言われているんだなと思いました。そこから子育てに真剣に向き合って楽しむようになりましたね。
そんな性格なので、「医者になる」と宣言した時、夫や母、お姑さんも身近で反対する人はいませんでした。反対してもしょうがない、反対してもやる人だからって思われているんだと思います。夫は「長期戦になりそうだけど、納得するまでやったらいい」と思っていたそうです。
今の私は当初考えていた小児科医としての仕事とは全然違うことをしています。置かれた場所で活躍できないなと思うときは、別の場所を探すことも選択肢のひとつです。子どもたちもまた、今の環境で自分の良さを発揮できていない、楽しくないと感じていても、別のところに活躍できる場所がきっとあります。
科学的な知見による子育てのプログラムと自分の経験や知見を活かして、困っている、悩んでいる親子の力となれるよう取り組んでいきたいという想いで活動しています。
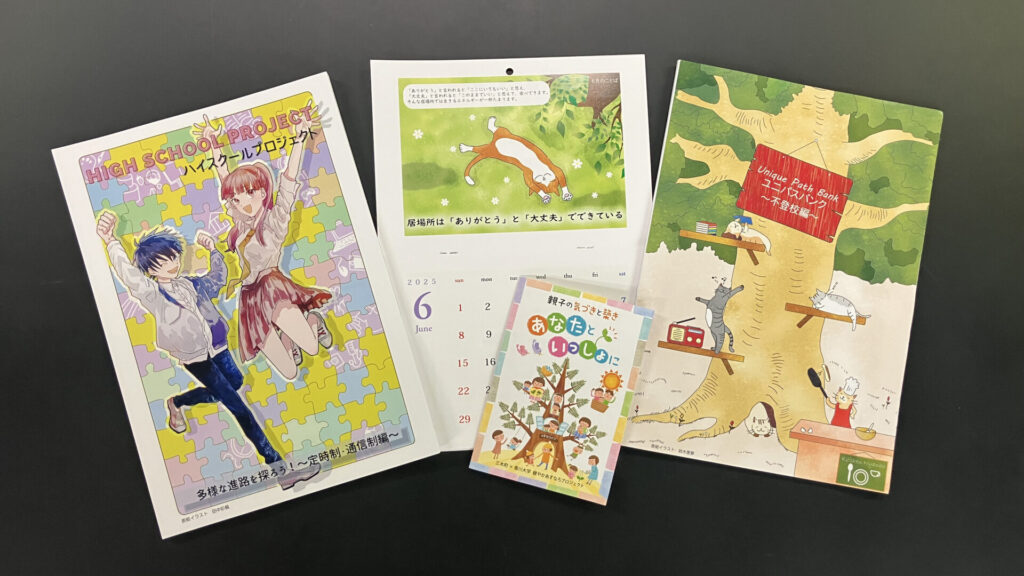
笑って1日を終える
―最後に、鈴木先生のリフレッシュ方法やリセット方法を教えてください
そうですね、人間関係でモヤモヤした時は「1:2:7の法則」で乗り切っています。
自分の周りの1割の人はあなたを否定し攻撃をしてくる、その2倍の2割の人はあなたに好意があり応援してくれる、7割は無関心と言われています。
私は過去にインターネット上のコメントで色々書かれたことがあって、この法則を身をもって体験しました。ネガティブなコメントってどうしても目についてしまって最初はモヤモヤしたのですが、この法則を知って「否定的な人は1割だけ、9割の人は好意的か無関心なんだな。それならその”1”の人は無視しちゃえばいいや」と思うと、特に気にならなくなりました。今では逆にネタにしちゃうくらいです(笑)。

あとは必ず笑って1日を終えるようにしています。
寝る前って「なんであんなことしちゃったんだろう」とか「なんで言えなかったんだろう」とかつい考えてしまうことがありますよね。「なんでなんで攻撃」をするとアドレナリンが出て眠れなくなるんですね。
でもね、人って同じ時間に2つのことを同時に思考することはできない、1つのことしか考えられないじゃないですか。だから「なんで」って考えないように、他のことをするといいんです。「考えちゃダメ」って思うと余計考えちゃうから、考えないために別のことを考えるルーティンを作るといいですね。
私は、寝る前にYoutubeでお笑いを見ることをルーティンにしています。最近は娘に教えてもらって、お笑いコンビ「レインボー」さんのYouTubeを見始めたのですが、今は娘に呆れられるくらいはまっています。すごくおもしろいですよ。
みなさんにも「なんでなんで攻撃」にはまらないように就寝前のお楽しみルーティンを作ることをお勧めします。
(取材:2024年12月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。