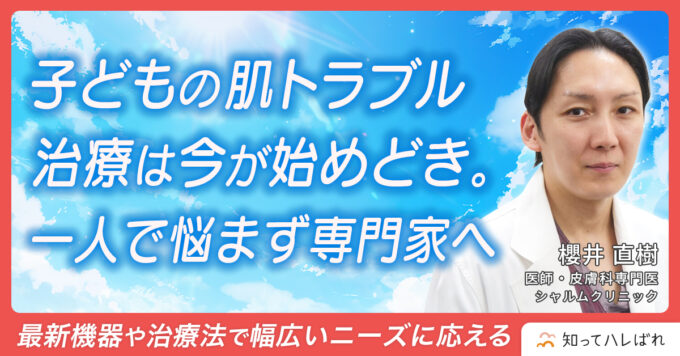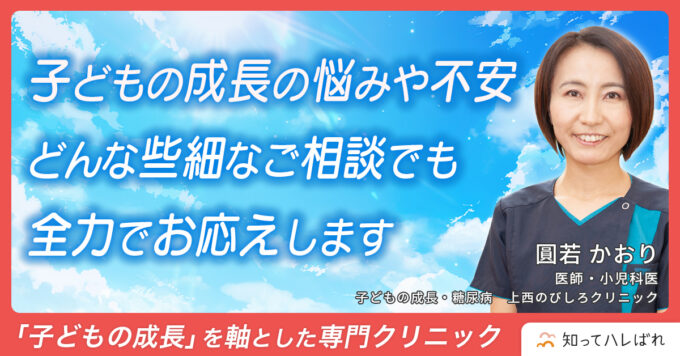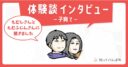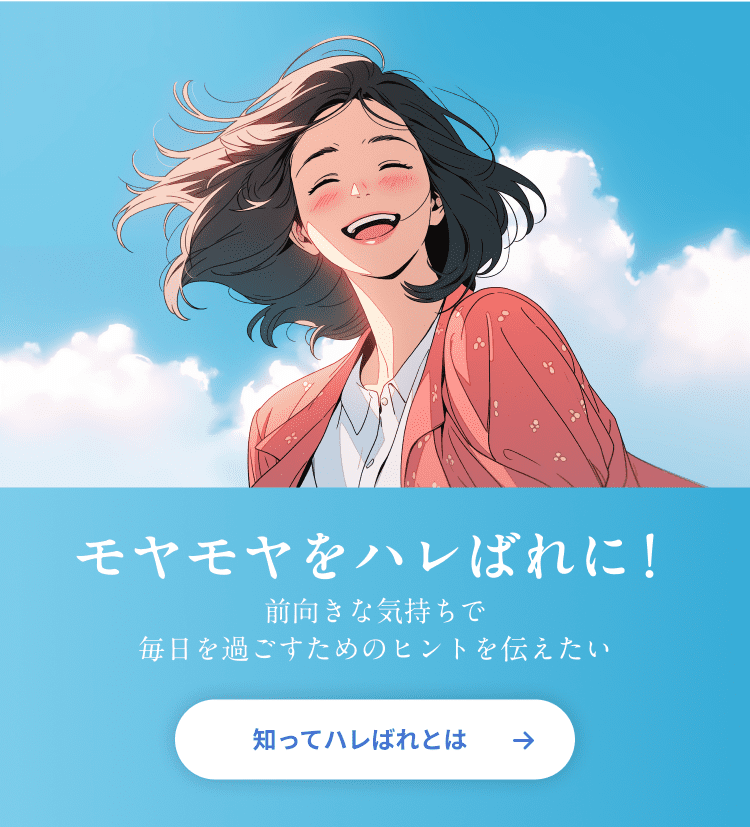子どもの性器について知ることは“正しい性教育”への第一歩【医師 岡田 百合香】

女性医師として泌尿器疾患に関わる日々
ー先生が医師を目指されたきっかけは何だったのでしょうか
実はこれといったエピソードがあるわけではありません。高校2年生くらいまでは、目の前のテストや部活動、友人との関係や恋愛に夢中で、自分の将来の職業について具体的に考える機会はほとんどありませんでした。
しかし、いよいよ「大学受験」が現実的になってきた時期に、親や先生から医学部という選択肢を勧められました。そこから医学部に関する本を読んだり、大学のイベントに参加したりする中で、多くの人のために働ける医師ってやりがいがありそうだな、と次第に関心が高まっていきました。
もともと幼いころから、人の生死や生きる意味に興味を持っていたこともあり、医学部を目指すための勉強はとても楽しく感じました。
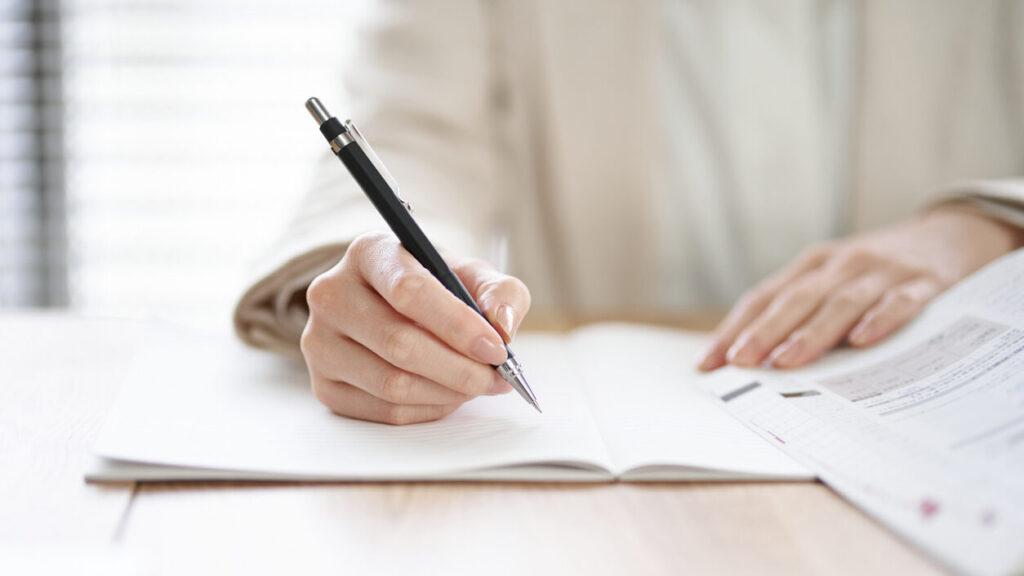
ー泌尿器科を専門として選ばれたのはなぜですか
研修医として様々な科を回ったときに泌尿器科にとても素敵な先生がいらっしゃって、自分もその先生みたいになりたい、先生のもとで勉強したいと思ったのがきっかけです。
泌尿器科は性や排泄に関する領域です。女性の患者さんも多くいらっしゃる一方で、医師は男性が圧倒的に多いことから、女性医師として何かお役に立てることがあるのではないかという思いもありました。
ー泌尿器科では、どのような患者さんや疾患を診ることが多いですか
腎臓や尿管、尿道、膀胱などの尿に関する臓器にまつわる疾患の診療を行っています。それに加えて、男性の生殖器や男性ホルモン、その他性的な悩みなどといった、男性の産婦人科的な側面もありますね。
ただ、病院の規模などによって、どのような疾患を診ることが多いかは変わってくると思います。私が以前勤務していた総合病院では、膀胱がんや前立腺がんなどの、がん患者さんを診ることが多かったです。あとは、トイレが近かったり、尿漏れをしてしまったりといった、尿トラブルの相談も多かったですね。
患者さんの男女比でいうと、男性が7割、女性が3割程度といった印象です。やはり男性患者の方が多いので、泌尿器科は、女性にとってはあまり馴染みがないかもしれませんね。
「おちんちん講座」で子どもの性器に関する疑問を解消
ー先生はママやパパに向けた「おちんちん講座」を実施されていますが、この講座を始めたのはどのようなきっかけからでしょうか
「おちんちん講座」を始めることになったのは、私自身の子育てがきっかけです。
出産後、地域の助産院で母乳マッサージなどの産後ケアを受けていたとき、助産師さんから、男の子を育てているお母さんたちが「性器のケアってどうすればいいの?」と悩んでいるという話を聞きました。助産師さんたちも専門外で困っていて、泌尿器科医である私に、そうした疑問にこたえるミニ講座を開いてもらえないか、と相談されたんです。
それで私も、ちょっとやってみてもいいかなと思って、助産院を利用しているお母さんたち10人くらいを対象に、おしゃべりを交えた気軽な感じで参加できる講座を実施しました。それが私にとって初めての活動です。


ーご自身の子育ての経験から始まった取り組みなのですね。取り組みを始めた頃の反響はどうでしたか
子どもの性器ケアについては、私が当初想像していた以上に大きな反響があり、「こんなにも知りたいと思っている方がいたのか」と驚きました。
「これまで悩んでいたけれど、誰にも聞けなかった」「性器の話をこんなに楽しく学べるなんてびっくり」といったうれしい感想をたくさんいただき、「こうした形でも、医師としての経験や知識を社会のために役立てられるのだ」と実感しました。
私は新聞を読むのが好きで、たまに投書をすることもあるんです。あるとき「おちんちん講座」のことを投稿したら、それが掲載されました。「こんな活動をしていて、参加してくれた皆さんが“勉強になった”“ありがとう”と喜んでくれて、とてもやりがいを感じています」といった内容だったと思います。
その投稿を、たまたま育児メディアの『たまひよ』の編集者さんが目にとめてくださったようで、「コラムを書いてみませんか?」と声をかけてもらったんです。そこからこの活動が少しずつ広がっていきました。
現在はオンラインも活用しながら、全国各地で子育て中の保護者の方々や、子育てに関わる専門職の方々、さらには子どもや学生に向けても講演の機会をいただいています。
もともと私は「人に何かを教えること」が好きで、大学時代には家庭教師や塾講師のアルバイトに精を出していました。そうした経験もあってか、「先生の話は分かりやすい」「2時間の講演があっという間でした」といった感想をいただくことも多く、大きなやりがいを感じています。
また、ありがたいことに著書『泌尿器科医ママが伝えたい おちんちんの教科書』を出版する機会をいただきました。より多くの人に子どもの性器のケアや、性教育について伝えることができて、とても嬉しく思っています。
ーこういった取り組みに対して、子育てをするお父さんたちの反応はどうでしょうか
「おちんちん講座」への参加者は、はじめのころはお母さんしかいませんでした。
そこから少しずつご夫婦での参加が増え、最近ではお父さんがお子さんを連れて参加する姿もよく見かけるようになりました。多くの方が「お話が聞けてよかったです!」とポジティブな感想を寄せてくださり、講座のあとにとても熱心に質問してくれるお父さんもいます。
なかには、「自分が思春期の頃に、こんな(性器に関する)嫌な体験があって…」と、貴重なお話を聞かせてくれる方もいて、お父さんの参加は私にとってもありがたいことだと感じています。

「専門家×子育て中の母親」が私の強みではあるのですが、育児の負担が女性に偏りがちな現状に対して、つい男性側を責めるような言い方になってしまうこともあります。
「性」に関する講座に参加してくれるお父さんはまだ全体の中の一部かもしれませんが、そういった意欲のある方々の声に丁寧に耳を傾けながら、父親にも届く講座のかたちを、これからも模索していきたいと思っています。
感性が豊かな子どものときこそ、性教育が必要
ー著書の中でも、子どもの頃からの性教育の大切さについて触れられていますが、性教育についてはどのような取り組みをされていますか
「おちんちん講座」では、性器のケアの話だけでなく、性教育についても必ずお話をしています。性器の話と、性教育の話は切っても切り離せない関係にあり、たとえば性器ケアの中で「包茎」について触れる際には、「ルッキズム(外見至上主義)」の問題についてもあわせてお伝えしています。こうした背景も含めてお話しすることで、より深く理解していただけると考えています。
性教育というのは、子どもだけのものではなく、大人の日常的な悩みや問題とも直結しているテーマです。「子どもには必要だけど、大人には関係ないよね」という捉え方ではなく、参加された方が「自分ごと」として受け止められるように、伝え方の工夫をしています。
文化や宗教、価値観など、明確な“正解”がないテーマも多いため、「専門家が正しい答えを教える」というスタンスではなく、「みなさんはどう思いますか?」と問いかけながら、一緒に考えていく姿勢を大切にしています。
また、各ご家庭で行う「おうち性教育」ももちろん大切なのですが、保育園や幼稚園、学校など、家庭の外でも性教育の機会をつくっていきたいと考えています。
性教育に関心のない家庭や、残念ながら暴力が存在する家庭も現実には存在します。どんな環境で育つ子どもにも等しく性教育が届くように、子どもに関わる専門職の方々との連携にも力を入れているところです。
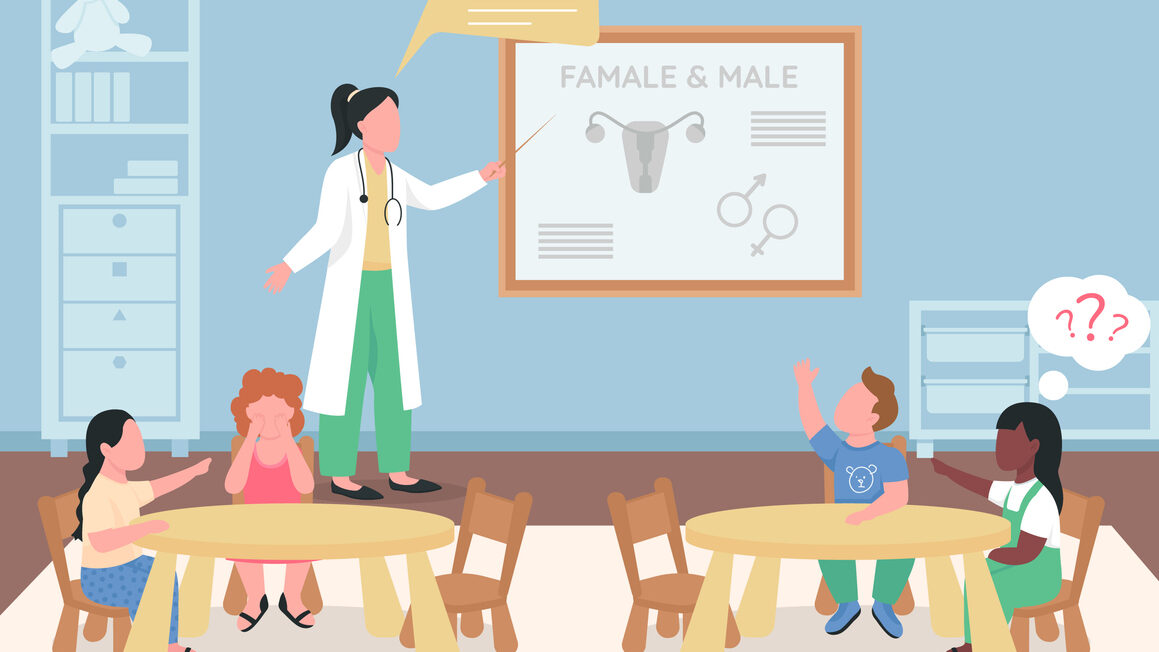
先日も学校の先生向けに勉強会を実施して、ワークショップ形式で先生方の性教育に関する悩みを話し合う機会をもうけました。その中では、「学校でも、もっと性について伝えていきたいけれど保護者との連携が難しい」といった声も聞こえてきました。
先生方も、性教育に対して高い意識を持ってくれているのだなと感じたと同時に、実践となるとあともう一歩乗り越えるべきハードルがあるのかなという気がしています。
子どもたちへの性教育へのアプローチとして、障害のあるお子さんへの取り組みにも力を入れています。昨年は、放課後等デイサービス(放デイ)を利用している子どもたちに向けて、性教育の講座を行いました。
講座の冒頭、性器の話題が出た瞬間はざわついたり、くすくすと笑い声が上がったりしたのですが、こちらが丁寧に、一生懸命に伝えていくうちに、子どもたちの表情も真剣なものになっていきました。
後日、参加していた放デイのスタッフから「子ども同士でふざけて性器を触り合うことが日常茶飯事だったのですが、講座のあとに『そこは俺のプライベートゾーンだから触るな』と子どもが言えていたんです」と教えていただきました。この話を聞いて、子どもたちに直接伝えることの大切さを再確認しました。
子どもたちの頭はとても柔らかくて、丁寧に伝えればきちんと受け止めてくれるんですよね。だからこそ、もっともっと正しい情報を、子どもたちに届けていきたいと強く思っています。

ー先生の今後の目標や展望について聞かせていただけますか
これからも、保護者の皆さんや子育てに関わる方々に向けた情報発信は続けていきたいと思っていますが、それに加えて今後もっと力を入れていきたいのが、保育園や学校といった「組織」へのアプローチです。
心身のケアや育児サポート、性教育といったものに、もっと気軽にアクセスできるような仕組みづくりに、医師として関わっていきたいと考えています。
教育現場で性教育がもっと自然に、そして活発に行われるようにするために、医師として私にできることがないか模索しているところです。また、海外ではどのような取り組みをしているのか、現地で実際に学んでみたいという思いもあります。
また、「おちんちん講座」などで情報をお届けするときには、できるだけ保護者の方の負担が増えすぎないよういつも意識しています。これからも、そのスタンスは大切にしていきたいと思っています。
「やるべきことをどんどん足していく」というよりは、「やらなくていいことは思いきって引いていく」というイメージです。私自身、子育ての中で「大変だな」と感じる瞬間があります。だからこそ、無理に押しつけるのではなく、そっと寄り添うような伝え方を心がけていきたいと思っています。
夢中になれる時間を持つことで心もハレばれ
ー最後になりますが、先生が心をリフレッシュさせるために実践していることを教えてください
リフレッシュしたいときは、何かに夢中になるのが一番だと思います。
私のリフレッシュに必要不可欠な存在はバレーボールです。学生時代からずっと続けているのですが、今はママさんバレーのチームに所属して、週2回ほど汗を流してリフレッシュしています。
普段仕事や子育てをしていると常に頭はフル回転で、あれもこれもとマルチタスクに追われています。バレーボール中は「目の前のボールを落とさないこと」だけに集中して、全力で喜んだり悔しがったりするわけです。
バレーの試合に勝とうが負けようが、給料が変わるわけでもないし、子どもの成績に影響があるわけでもありません(笑)。それでも、ただ楽しいから、もっと上手くなりたいから、という内から湧き上がる純粋な動機によって、「母」でも「医師」でもない自分として所属できる場というのは本当に大切な存在です。
人生において「この時間楽しい」と思えるひとときを持つことは、毎日をいきいきと過ごすためにも大切なことではないでしょうか。自分の子どもにも、何か夢中になれる楽しみを見つけてもらえたらと思っています。
(取材:2025年2月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。