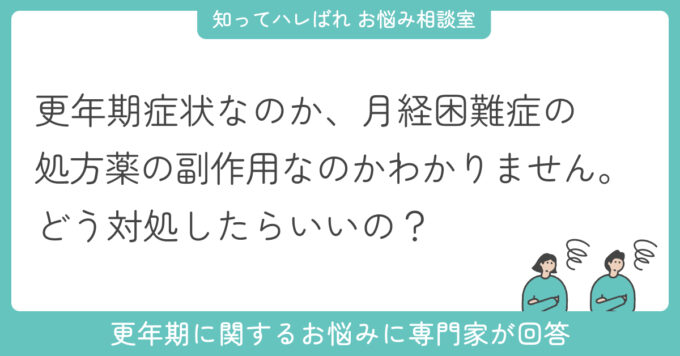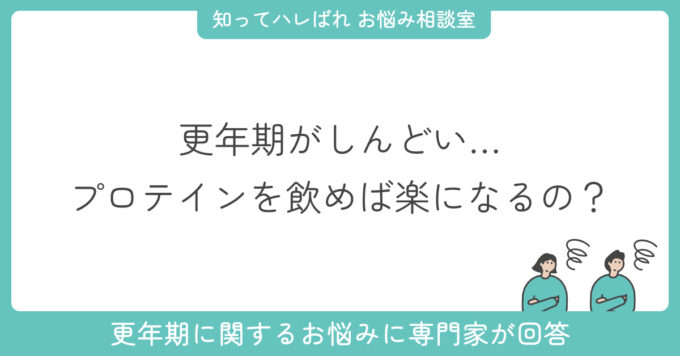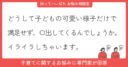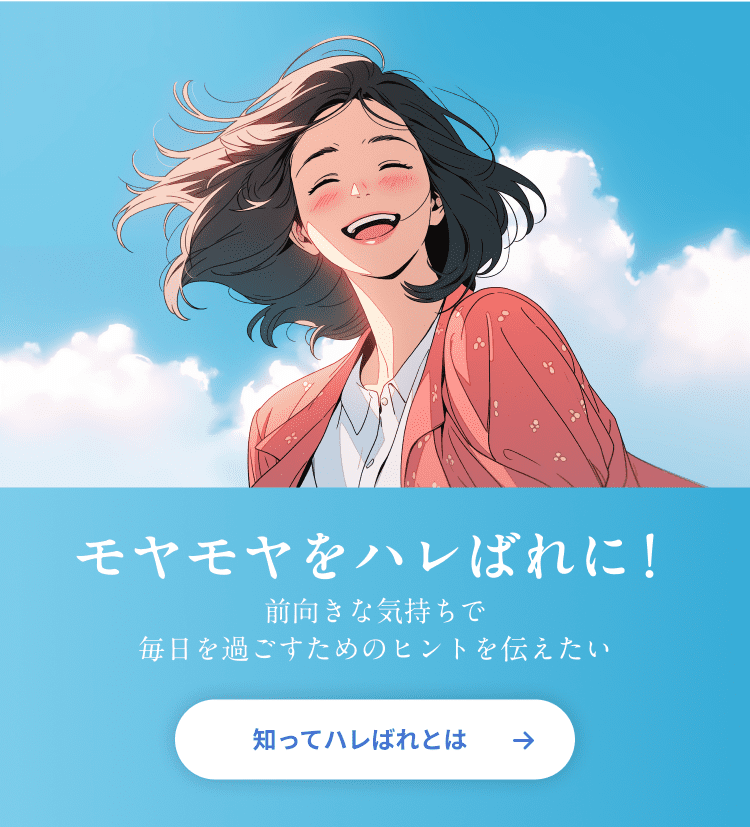「更年期」は努力と心の持ちようで輝く自分に変わる時【医師 丹羽 咲江】
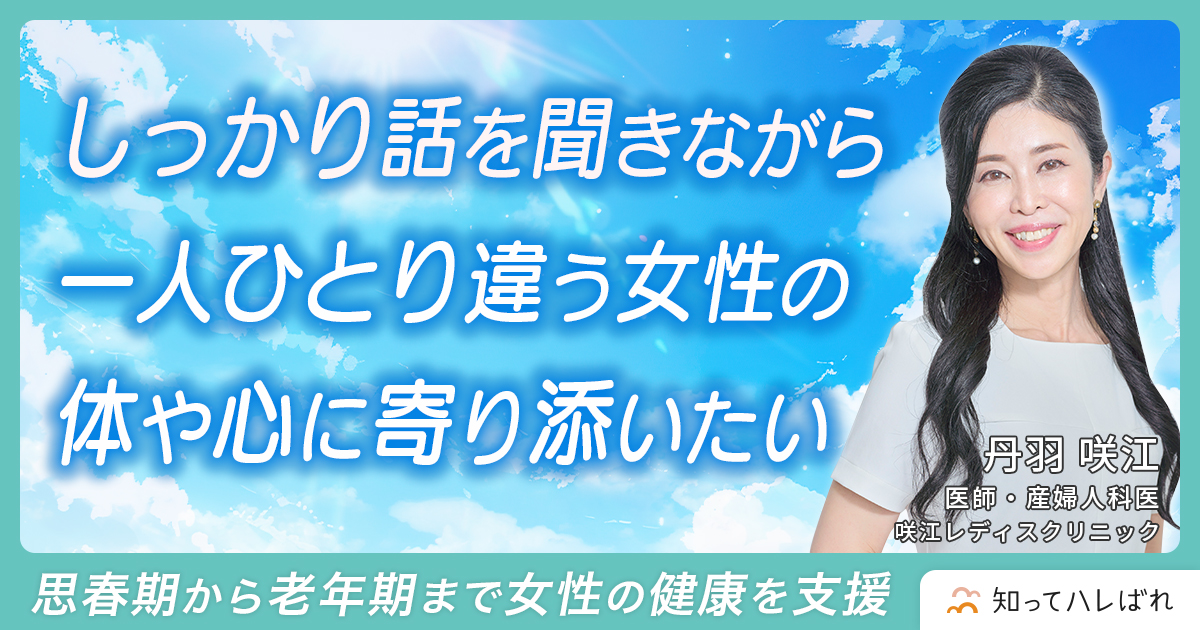
目次
自然と目指した医師への道、ジェンダーギャップに苦しむ女性をサポートしたい
ー丹羽先生が産婦人科医を目指すようになったきっかけを教えてください
産婦人科医の父の影響から、病院が身近な環境で育ったことで自然と医師を目指すようになりました。
父親が産婦人科の開業医で、自宅に隣接する病院が私の日常的な居場所のひとつでした。朝から晩まで病院で過ごしながら「将来はお父さんと一緒に仕事がしたいな」と思ったのが医師を目指した最初のきっかけですね。
実際に産婦人科医となった理由は、私自身が女性として様々な不条理な経験をする中で、「女性の駆け込み寺のような場所を作りたい」という強い使命感のような想いを持つようになったからです。
私が医学部に入学した当時は、高学歴な女子学生は「女のくせに」と言われるような時代でした。大学にあまりなじめず学外で遊び倒した学生時代でした。
医師になってからも、女性は結婚して子どもを産むから長くは勤務しないだろうという理由で、「当直の回数は減らす」「手術に熱心でなくて良い」などという雰囲気があり、懸命に働きたいのに叶わない理不尽な思いをしました。
私生活でも、DVという概念さえなかった時代に夫からのモラハラを受け、心身ともに疲弊し30代後半でプレ更年期のような症状に悩まされました。
私自身、女性が社会的に不利な立場にあることを痛感する経験を通して、「人生で一番大切なのは自分自身」だと気づきました。女性が自分自身を大切にする意識を持つように、そしてそのためのサポートをしたい。そうした思いと、自らの経験を活かしたいという思いから、現在の活動に至っています。

ー現在はまさに「駆け込み寺」のような、クリニックの内外で、若年層から更年期、老年期の方まで幅広く支援されていますよね
高校生や大学生に向けた性教育では、予期しない妊娠を未然に防ぐ教育のほか、人と触れ合うことの幸せを正しく知ってほしいという想いで取り組んでいます。
また「街角保健室」と称して、繁華街にある公園で夜にテントを張って10〜20代の女の子が気軽に立ち寄って相談できる場を提供しています。生理の話を聞きながら妊娠や性病などの医療相談につなげることで、自分を大切にすることを伝えていきたいと思っています。

クリニックでは、患者さんの人生に深く関わる悩みにも向き合うようになりました。たとえば、子育てが一段落し、新たなパートナーができたものの、「久しぶりにセックスしようと思ったらできなくなっていた」と悩む女性は少なくありません。そういった方に心身のメンテナンスや施術をおこない、性的な健康を取り戻すお手伝いをしています。「生まれてはじめて女性として生まれてきて良かったと思えた」「やっと幸せになれた」という声を多く聞くようになり、大きなやりがいを感じています。
いつかこのクリニックの場所に「池下観音※」をつくって、女性のためのパワースポットにしたいというのが将来的な目標です(笑)。
※咲江レディスクリニックが名古屋市千種区“池下”に所在しているため
婦人科受診の“不安”と“痛み”を取り除くための努力は惜しまない
ー普段の診療で先生が心がけていることはどのようなことでしょうか
クリニックは安心安全な場所でなくてはならないと思っています。患者さんにとって分かりやすい説明を心がけ、来院時に「怖い」と思わず、心が安らぎ、帰る時には「良かった」と思えるような場所にしたいと思っています。院内も病院らしくない可愛らしい雰囲気にしているんですよ。


特に、話し方や声のトーンが大切だと考えています。もともと人前で話すことは得意ではなかったのですが、あがり症克服の講座受講やFM局主催のアナウンススクール、ボイストレーニングなどに長年通い、患者さんが安心できる声や話し方を身につけるよう努力をしています。
せっかく女性の医師に相談しようと思って来院してくれた患者さんを怖がらせてしまっては、婦人科を受診すること自体がトラウマになってしまうかもしれません。そうならないよう、私自身の努力は惜しみません。
そしてなにより、「やさしさ」「丁寧」「痛くない診療」をモットーに痛くない診察にこだわりがあります。
デリケートな女性のからだに負担をかけないよう、当院では様々な器具を取り揃え患者さんに合わせて使い分けています。特に内診で使用する器具は、特注サイズの器具を引退した職人にお願いして作成しています。患者さんのからだに合わせて使い分けることで、できる限り痛みを抑えた診察を提供しています。
ー 患者さんと接する中でやりがいを感じるのはどんな時ですか
患者さんの人生の様々なステージに寄り添い、変化を見守ることにやりがいを感じます。
例えば、14、5歳で援助交際や中絶を繰り返していた子が、20歳を過ぎて「今度こそ産む」と言って出産後にうれしそうに赤ちゃんを連れてきてくれた時。繁華街で薬を大量に飲んで倒れていた家出少女を保護し児童相談所に連絡した結果、半年後にしっかり更生し「あの時先生に出会えて良かった」と笑顔で言われた時。シングルマザーで生活や子育てに苦労していたお母さんが、50歳を過ぎて自分の幸せを見つけ「今、本当に幸せです」と語ってくれた時などです。
患者さんの人生の長い経過を見守れるのもこの仕事の醍醐味です。私が初めて妊婦健診をした方が、今度は自分の子どもを連れて妊婦健診に来てくれたり、父の代から診ていた患者さんが更年期症状で来院し、今度は娘さんも…という風に、長いお付き合いができるのは本当に嬉しいです。
何十年も前の患者さんが、今でも元気でいてくれるのを見ると、この仕事をやっていて良かったと心から思います。
更年期をハレばれと過ごすコツは当たり前のことをきちんとやること
ー更年期の患者さんからよく聞くお悩みはどんなことでしょうか
更年期の患者さんからよく聞くお悩みは、「こんな症状で病院に来て良いのか」と受診自体をためらっている方が多いですね。あとは「どんな治療が自分に合うのか分からない」「生活で何に気をつけたら良いのか」という相談も多いです。
更年期症状は自律神経の乱れが原因なので、ストレスや過労など自律神経が乱れる原因を避けることが大切です。「無理をしない」「よく寝る」「ストレッチや筋トレをする」など、基本的な生活習慣の見直しをおすすめしています。

最近は「膣の緩み」や「尿失禁」の相談も多いです。施術を行うことで改善することもありますが、そうでない場合は、やはりご自身でトレーニングをしていただくなどある程度の努力も必要になります。
せっかく受診したのに医師から「ご自身の努力です」と言われ、患者さんとしては「見捨てられた」と感じてしまわないように、努力の必要性を伝えるための言葉選びには気を配っています。
ー更年期をハレばれと過ごすコツはありますか
まず「自分を追い込まない」ことが大切です。年齢的にも今までできていたことができなくなる、やる気が出ない、気分が沈む、ネガティブになるなど、更年期の症状は辛いですよね。
女性ホルモンが減ることが原因のひとつなので、お薬やサプリメント、ホルモン補充療法などで対策するのも良いですが、自然に乗り越えるには、先ほどもお話ししたように自律神経を乱すようなことを避ける生活を心がけてください。
痩せすぎにも注意が必要です。女性ホルモンは卵巣からの分泌以外にコレステロールからも作られるので、痩せすぎると女性ホルモンが枯渇してしまいます。かといって、太りすぎも他の疾患の原因になることもあるので避けてほしいですね。
更年期を健康に過ごすコツとしては、「適正体重を維持し、よく寝て、当たり前のことをきちんとやる」この3つをいつもお伝えしています。
そして、時には整体やマッサージなど、自分へのご褒美も大切にしてください。

ー読者へのメッセージをお願いします
更年期は人生の折り返し地点。後半戦は、努力と心の持ちようで輝く自分に変わることができます。
症状のつらさなどもありますが、更年期は老年期にジャンプするためのちょっとしたハードルです。ポンと飛び越えてしまったら、元気なおばあちゃんになった自分が待っているので心配しすぎなくて大丈夫です。
迷った時は誰かを頼ってスパッと決める
ー丹羽先生の気分転換やリフレッシュ方法を教えてください
「健全なる精神は健全なる身体に宿る」という言葉通り、体の管理を怠らず、しっかり食べてしっかり寝ることは、私にとって健康に生きるためのテーマです。
モヤモヤしないために、信頼して相談できる人がいると良いですよね。私は普段からなるべく悩まないように心がけてはいますが、どうしても決められない時は、問題を分割して小さなことから決めていくことをしています。
どんな風に決めても、最終的な結果は決まっているような気がします。自分の信念に基づき、人を騙したり陥れたりせず正しくやるべきことをしていれば、最終的にはどちらを選んでも同じ方向に進むのではないでしょうか。それに、何事も決断し続けることで、自分のパターンがわかってきたり、勘がより鋭くなったりすることがあるといった良いこともあると思います。
それでも人間ですから悩むもの。そんな時は、信頼できる人に相談するか、小さなことから決めるなどして、スパッと決めてしまうのも良いと思います。
(取材:2025年2月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。