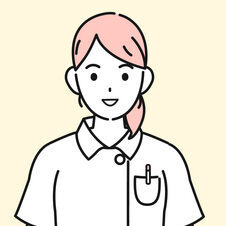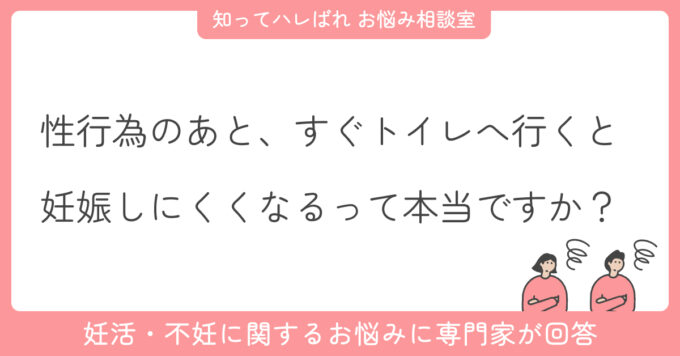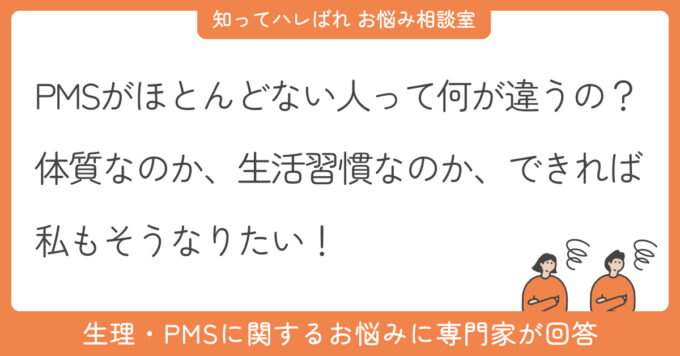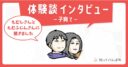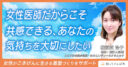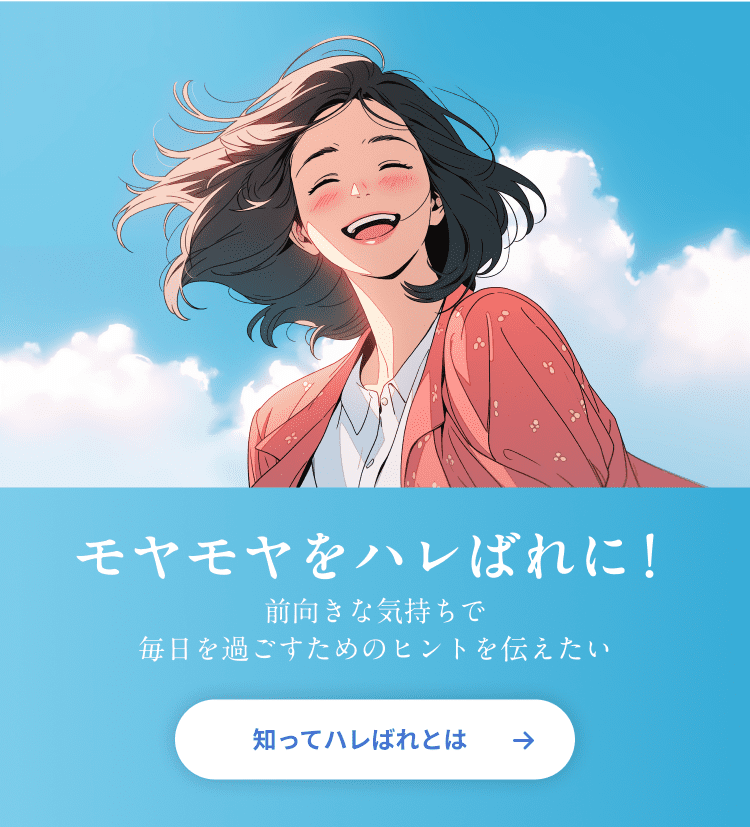疲れているのに眠れない…更年期の睡眠トラブル【お悩み相談室】
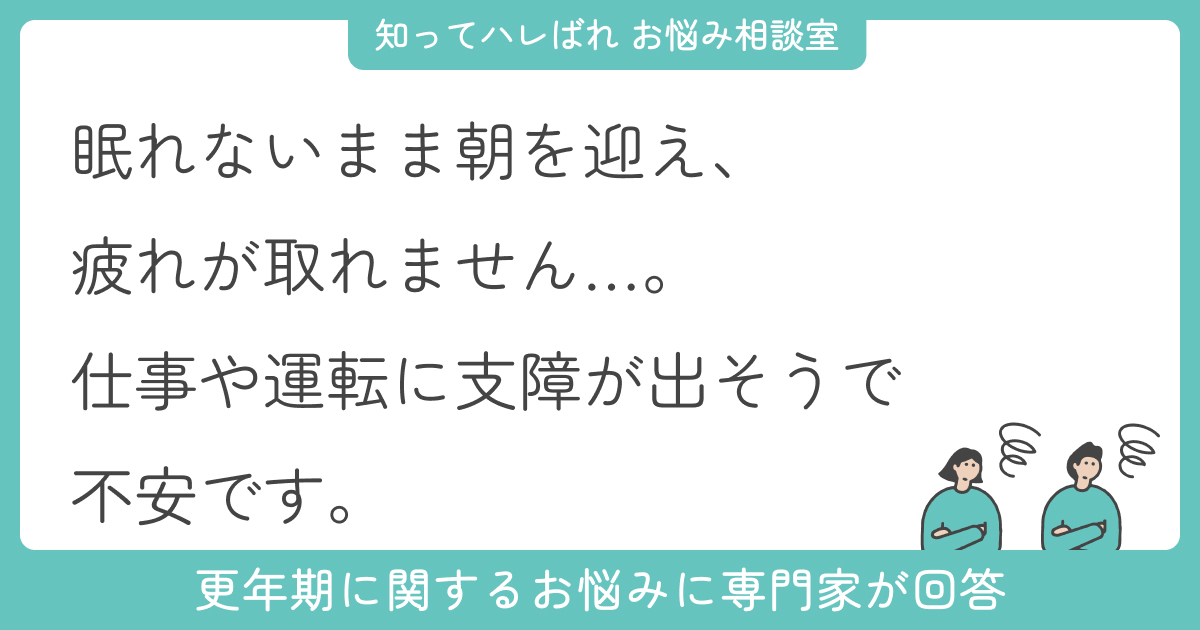
更年期の不眠に悩む方からのご相談です。疲れているのに寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚め、朝も早く起きてしまうとのこと。薬には頼りたくないものの、生活習慣を見直しても改善されず、仕事や健康への影響が不安だそうです。
更年期による睡眠トラブルを軽減し、質の良い眠りを得るための方法について助産師がアドバイスします。
更年期の不眠に悩んでいます。日中の運動量に関わらず寝付きが悪く、やっと寝付けても夜中に何度も目が覚めて、またしばらく寝付けません。
時間的にはあまり眠れていないはずなのに朝は朝で早くに目が覚めてしまいます。
これ以上横になっていても眠れないので、明け方の早くに起きて、まだ暗いうちからゴソゴソと家事を始めますが、疲れがとれず常に身体がだるかったり、頭もボーっとしてしまいます。
家族に「疲れていても眠れない」と言ったら、「薬を処方してもらったら?」と言われますが、薬がないとますます眠れなくなりそうで躊躇しています。
夕食後に飲んでいたコーヒーをやめてみたり、部屋の照明を落として暗くしてみたりしましたが改善されません。
今後、このまま不眠が続くことによっておこる健康被害が心配です。
また集中力や判断力の低下によって、仕事のミスや車の運転等に支障が生じないか不安です。アドバイスいただけますと幸いです。
(50代、女性、ハンドルネーム:hisa41、職種:主婦)
目次
最初に
更年期に入ると、これまで経験したことのないような心身の不調に直面することがあります。
その中でも「眠れない」「疲れがとれない」といった睡眠の悩みは、多くの方が共通して抱える深刻な問題です。
ご相談のように、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早くに目が覚めてしまうといった状態が続くと、体力だけでなく気力まで奪われてしまいますよね。
まず、こうした状態がご自身の努力不足や意志の弱さによるものではないということを、ぜひ知っていただきたいと思います。
更年期に起きる不眠は、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少や、自律神経の乱れによって起こる「体の自然な変化」です。
心の問題だけでなく、体の変化が深く関係しているため、「寝ようとしても眠れない」ということが起きるのは、ごく自然な反応ということを知っておくといいですね。
更年期へのアプローチ3選
ご自身でも、カフェインを控えたり、照明を落としたりと生活習慣の工夫をされていて素晴らしいと思います。
こういった努力は結果が分かりにくくても、確実にプラスの影響を与えているはずです。
そのうえで、もし今の方法で改善が難しい場合は、いくつか別のアプローチも検討してみてはいかがでしょうか。
体のバランスを整える「漢方」という選択肢
西洋医学の睡眠薬に抵抗がある方にとって、漢方薬は非常に心強い選択肢のひとつです。
漢方は「症状を抑える」のではなく、「体の根本的なバランスを整える」ことを目的としているため、更年期のように原因が複雑な不調にはとても有効とされています。
たとえば、イライラや不安感が強く眠れない方には【加味逍遥散(かみしょうようさん)】、
心の高ぶりや神経の緊張が強い方には【抑肝散(よくかんさん)】、
血行が悪くのぼせや冷えを感じる方には【桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)】、
不眠そのものが中心で「眠れないことがつらい」方には【酸棗仁湯(さんそうにんとう)】などが用いられます。
ただし、漢方は体質や体の状態に合わせて処方されるものですので、自己判断ではなく、漢方に詳しい婦人科医や薬剤師に相談して選ぶのが理想です。
副作用が少なく、長期的な体質改善が期待できる点も安心ですね。
睡眠リズムを整える生活の工夫
すでに実践されている内容に加え、次のような習慣も効果が期待できるかもしれません。
朝の光を浴びる:
睡眠と覚醒のリズムには「光」が大きく影響します。
毎朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の眠気が自然に訪れやすくなります。
一方で、夜はスマホやパソコンなどのブルーライトを避けましょう。
「寝る前の儀式」をつくる:
アロマ、ストレッチ、ハーブティー、読書など、「眠る前はこれをする」というルーティンがあると、脳が「そろそろ眠る時間だ」と認識しやすくなります。
ぬるめのお風呂にゆっくり入る:
38~40度程度のぬるま湯に20分ほど浸かると、副交感神経が優位になり、自然と眠りやすい状態になります。
「薬=怖いもの」ではなく、選択肢のひとつとして
薬への抵抗があるお気持ち、よく分かります。
「薬に頼ってしまったら、もう自然には眠れなくなるのでは」と心配になりますよね。
ただ、近年は依存性の少ない睡眠導入薬や、自然由来のサプリメントなども多く登場しています。
大切なのは、「ずっと飲み続けること」ではなく、「一時的に心身を休ませるサポート」として薬を上手に使うことです。
つらい状態が続くと、心身ともに回復しづらくなってしまうこともあるため、必要に応じて医師と相談しながら、最適な方法を選ぶことがご自身の体を守ることにもつながると思います。
最後に
ご相談にある通り、不眠が続くことで疲労感、集中力の低下、判断ミス、交通事故などにつながる可能性は現実的にありえます。
仕事や家庭生活に支障が出る前に、「今、ケアをすること」は決して甘えではありません。
むしろ、これからの健康と生活の質を守るための大切な一歩です。
これまで頑張ってこられたご自身に、「よくやってるよ」と声をかけるつもりで、少しずつでも心と体を整える方法を試してみてくださいね。
そして、どうかひとりで悩まず、必要なときには周囲の助けも借りてください。
ご自身に合った良い眠りが戻ってくることを、心より願っています。
<参考文献・出典>
公益社団法人 日本産婦人科学会
▶更年期障害について:https://www.jsog.or.jp/citizen/5717/
更年期ラボ
▶更年期の不眠について:https://ko-nenkilab.jp/symptom/insomnia.html
クラシエ漢方療法
▶不眠特集:https://www.kracie.co.jp/ph/k-therapy/tokushu/insomnia/
Kampo view
▶更年期と漢方薬の解説:https://www.kampo-view.com/trouble/kounenki
Kampo view
▶不眠と漢方薬の解説:https://www.kampo-view.com/trouble/fumin
専門家がこたえます!お悩み募集中です
「知ってハレばれ お悩み相談室」にお悩みをお寄せください。
毎月ピックアップさせていただいたお悩みとその回答を、「知ってハレばれ お悩み相談室」の記事で公開いたします。下記のフォームからお悩みをお寄せください(匿名でお寄せいただけます)。