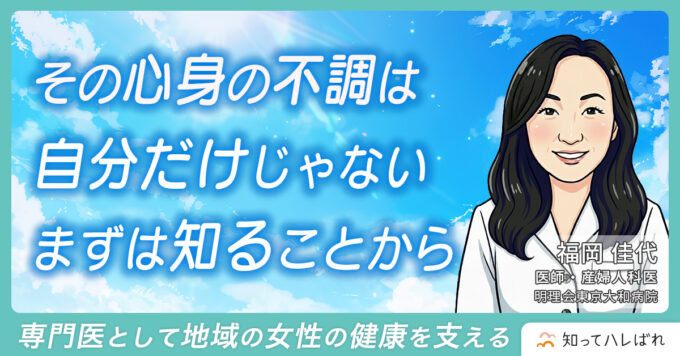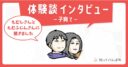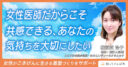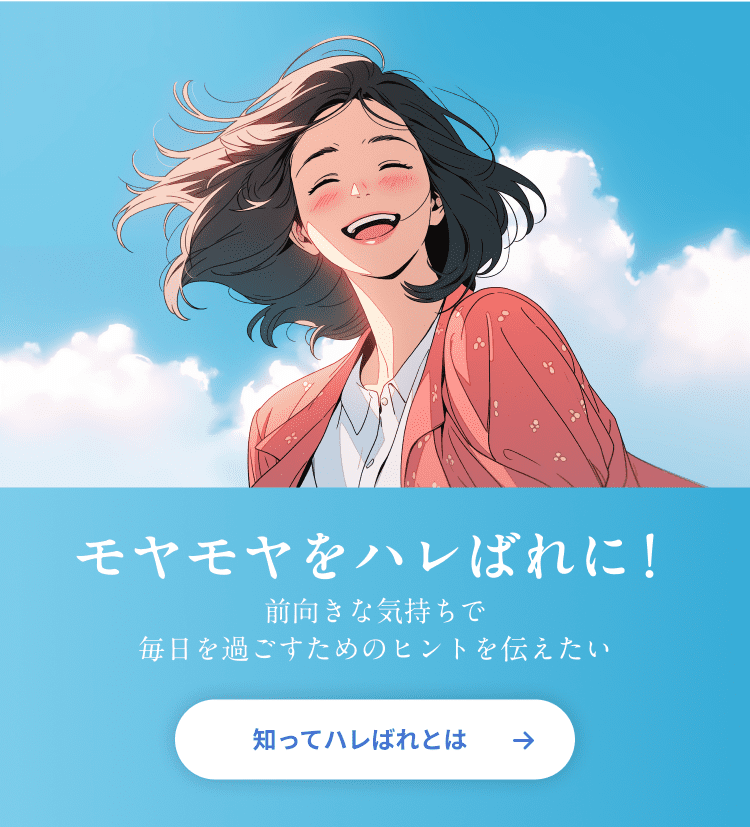その不調は「気のせいじゃない」。気象病に悩む方の力になれたら【医師 久手堅 司】
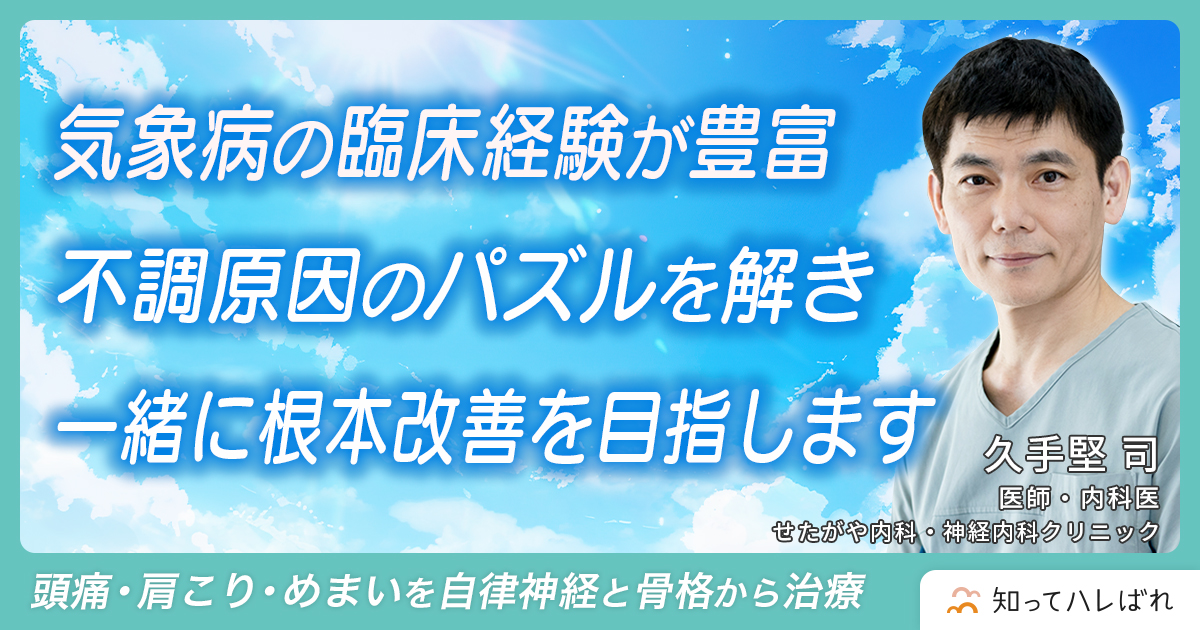
目次
「頭痛・肩こり・めまい」の専門医として開業
ー先生のご経歴と、頭痛や肩こりを専門としたクリニックを開業された経緯を教えてください
私の専門は内科と脳神経内科です。クリニックを開業する前は、大学病院や急性期病院で脳出血や脳梗塞といった命に関わる疾患を担当していました。ただ、実際の診療現場では、命に関わる病気だけでなく、いわゆる一次性頭痛(緊張型頭痛や片頭痛)や、首こり・肩こりに悩む患者さんも非常に多いことを実感していました。
頭痛や肩こりは命に関わるものではない一方で、日常生活の質を大きく左右します。そこで、頭痛や首・肩こりに悩む方をしっかりと診療したいという想いから、2013年8月に「せたがや内科・神経内科クリニック」を開業しました。

ー「気象病・天気病外来」「寒暖差疲労外来」などユニークな特殊外来の開設にはどのような背景があったのでしょうか
地域での診療を続ける中で、検査をしても異常が見つからない、でも「なんとなく体調が悪い」と感じている患者さんに多く出会うようになりました。特に女性の方に多く、「更年期障害」「自律神経失調症」などと診断されていても、なかなか改善しないというケースが目立っていました。
そうした患者さんの声に耳を傾けていると、「天気が崩れる前に頭が痛くなる」「雨の日は体がだるい」といった、“気象と体調の関係”を自覚している方がとても多いことに気づいたのです。
私自身、「気象病」という言葉は知っていたものの、専門的に診る機会はありませんでした。当時は気象病を専門に診療している医師は全国でもごくわずかで、多くの患者さんが相談先もなく悩んでいるという現実がありました。
気象病は一般的に知られている病名ではありませんが、実際に症状で苦しんでいる方がいる以上、決して軽視できるものではありません。
天候の変化による不調に悩んでいる方の声に応えたいという思いから、2016年に気象病を専門とした外来を開設しました。日々の診療で感じた目には見えない不調に寄り添いたいという気持ちが、専門の特殊外来を始めたきっかけです。

ー「気象病」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか
気圧や気温、湿度の気象変化によって引き起こされる心身の不調を「気象病」といいます。天気の変わり目に頭が痛い、めまいがする、だるい、肩こりがつらいなど、症状は人それぞれです。
特に影響が大きいのは「気圧」の変化です。患者さんの多くは、気圧が下がるときに体調が悪くなる傾向があります。「気温」や「湿度」の変化も体調に影響します。自律神経は環境に合わせて体温を調節していますが、1日の寒暖差が大きくなると自律神経ががんばりすぎてしまい、倦怠感につながります。
1年のうち、患者さんが最も多くなるのは、雨の続く梅雨シーズン。台風の時季にも増える傾向にあります。最近ではゲリラ豪雨など急激な天候や気圧の変化で不調を訴える方も増えています。
実は気象病というのは正式な「病名」ではありません。最近ではメディアに取り上げられる機会が増え、気象病の認知度も向上してきたと感じていますが、「気にしすぎ」「精神的なもの」など、まだまだつらさをわかってもらえずに苦しんでいる方も多いのではないかと感じています。
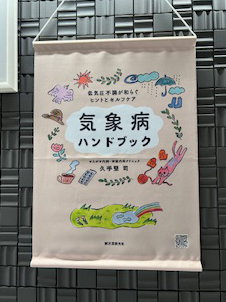
患者さんの声に耳を傾け、対処療法だけではなく根本原因を探って改善
ー診察時に特に心がけていることはありますか?
何よりも患者さんの話を丁寧に聞くことを心がけています。
その方の感じている不調や生活の様子を細かく聞き取ること、そして実際の体の状態(姿勢や歩き方、肩や首のこり具合など)をじっくりと観察します。「気のせい」「自律神経のせい」と言われて原因が分からなかった方も、丁寧な診察によって原因が判明することがあります。
例えば、産後に片側の頭痛が出るようになった方の場合、骨盤のゆがみが姿勢に影響して、首や肩に負担がかかっていることが原因でした。こういった「体のアンバランスさ」に、気圧や気温の変化が加わると、自律神経が乱れ不調が表れます。
頭痛、首こり・肩こり、めまい、倦怠感などを訴える方には、むくみや血行をよくする薬などの処方のほかに、ストレッチやマッサージ、気象病対策アプリによる気圧チェックなどをおすすめします。
それに加えて、トレーナーの指導のもとで自律神経に良い呼吸法や食事指導、運動療法、体のゆがみ改善なども行っていきます。

生活習慣の改善や骨格の歪みの改善で、不調や症状をゼロにすることはできませんが、10のつらさを5〜7に減らすことはできます。不調を増やさないよう、症状に合ったセルフケアを一緒に考えて実践していくことが大切だと考えています。
ー自律神経と骨格には密接な関係があると聞きましたが、骨格の歪みはどのように影響しているのでしょうか
自律神経は気象病と深く関わっていますが、実は骨格の歪みも自律神経の乱れの原因の一つになります。自律神経は単独で機能しているわけではなく、脳から脊髄を通じて全身に張り巡らされています。そのため、骨格に歪みが生じると、自律神経の働きに大きな影響を与える可能性があるのです。
特に現代人は、スマートフォンやパソコンの使用時間が長く、無意識のうちに下を向く姿勢をとりがちです。この習慣が首や背骨に負担をかけ、歪みやねじれを引き起こすことにつながります。脊髄は脳と全身をつなぐ重要な神経経路ですが、骨格が歪むことで神経が圧迫され、自律神経のバランスが乱れることがあります。その結果、頭痛、めまい、倦怠感、不眠など、さまざまな症状が現れるのです。
こうした不調を改善するためには、骨格の歪みを整えることが重要です。もちろん、完全に歪みをなくすことは難しいですが、適切なメンテナンスを行うことで症状を軽減することは可能です。
当院では、必要に応じてレントゲン撮影を行い、骨格の状態を詳しく確認しながら、患者さんに分かりやすく説明しています。「まさか自分の体の歪みが症状の原因だったとは思わなかった」と驚かれる方もいらっしゃいます。しかし、原因が分かれば、適切な治療を行うことで症状の改善につなげることができます。

また、日常生活の中でもストレッチや姿勢の改善、生活習慣の見直しを行うことで、骨格の歪みを防ぐことは可能です。私とパーソナルトレーナーの賀来大樹さんが監修した『いつでもどこでも背骨リセット』では、簡単にできるストレッチ方法を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
女性に多い体調不良、低血圧と自律神経の密接な関係
ー気象病や頭痛で来院される患者さんに、血圧測定を勧めることが多いそうですね
そうですね。特に女性には自宅での血圧測定をおすすめしています。というのも、低血圧や起立性調節障害※は女性に多く、さまざまな体調不良の原因になるからです。
※起立性調節障害(OD:orthostatic dysregulation):立ち上がった時に血圧が急激に低下し、めまいやふらつき、失神などの症状が現れる状態。朝なかなか起きられない、目覚めても頭痛や腹痛がして寝床から出られないなどの状態。
例えば、朝起きたときは血圧が低くても、通院する際に歩くことで血圧が上がっていることがあります。また、病院では緊張して血圧が上がる「白衣高血圧」の影響で、低血圧だと気づかれないケースもあります。そのため、リラックスした状態、特に朝起きたときの血圧を自宅で測ることが重要です。
低血圧の方は気圧の変化に敏感で、症状が悪化しやすい傾向があります。朝なかなか起き上がれない、立ちくらみ、めまい、頭痛、倦怠感など、さまざまな形で影響が出ます。これは、低血圧によって脳への血流が低下することが原因です。
自宅で定期的に血圧を測り、自分の変化を把握することが大切です。そのうえで、塩分や水分を意識的に摂ったり、下半身の筋トレをしたりすることで改善することができます。
ーなぜ女性は低血圧になる傾向があるのでしょうか
女性に低血圧が多いのは、ホルモンバランスや貧血が関係しています。生理による出血から貧血になりやすく、筋肉量がすくないことが、低血圧につながることがあります。
また、女性ホルモンの影響で、男性よりも血圧が低くなりやすい傾向があります。更年期になると女性ホルモンの分泌量が減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強くなるため、血圧が上がりやすくなります。
「気象病」は “気のせい” ではない
ー医師として、特にやりがいを感じる瞬間はどのような時ですか?
もちろん、患者さんの症状が改善し、元気になっていく姿を見るのは大きな喜びです。ただ、それと同じくらい、あるいはそれ以上に心に残るのが、初診の際に「やっと分かってくれる先生に出会えた」と言われた時です。
当院には、これまでにいくつもの医療機関を受診しても原因が分からず、不調に苦しんでいる方がたくさん来られます。特に気象病の患者さんは、天候と体調の関係をなかなか理解してもらえず、「気のせい」と言われてつらい思いをしてきた方が多いです。
そんな中で、当院で初めて「自分のつらさを分かってもらえた」と感じ、「先生だけが理解してくれた」と言われることがあります。その時には、医師としてこの仕事をしていて本当に良かったと、心の底から思います。
婦人科、内科、脳神経外科、整形外科、心療内科・精神科など、さまざまな医療機関を渡り歩き、それでも原因が分からずにいた患者さんが、最終的に当院にたどり着き、「ここでやっと理解してもらえた」と話してくれる。その瞬間の喜びは、何ものにも代えがたい大きなやりがいとなっています。

ー不調に悩む読者の方々へメッセージをお願いします。
もし、「この体調不良は何が原因なのか分からない」「どこに相談すればいいのか分からない」と悩んでいるなら、決して諦めないでください。どんな不調にも必ず原因があり、解決策もあります。
まずは、インターネットや書籍などを活用して情報を集めてみてください。私の著書や、ほかの専門家が発信する情報もきっと参考になるはずです。「そういえば雨の日は調子がでない」などご自身の症状と似たケースを調べるうちに、解決のヒントが見つかるかもしれません。
今後はクリニックでの診療に加え、講演会などを通じてより多くの方に気象病や体調管理について知っていただけるよう活動していきます。診療の場では一度にお伝えできる情報が限られますが、講演会などではより多くの方に知識や経験を共有できると考えています。
もし、原因が分からない不調に悩んでいるなら、どうか一人で抱え込まず、情報を集め、専門家に相談してみてください。きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。
「仕事以外の時間」を意識的につくってリフレッシュ
— 忙しい毎日の中で、どのようにリフレッシュされていますか
仕事に追われる日々だからこそ、意識的に「仕事以外の時間」を作るようにしています。診療だけでなく、執筆やメディア対応などもあるため、つい仕事中心の生活になりがちです。だからこそ、あえて仕事から離れる時間を確保するよう心がけています。
具体的には、外来のない木曜日や土曜の午後、日曜は、できるだけ仕事の予定を入れません。また、仕事を家に持ち帰らないことも意識しています。どうしてもやらなければならない仕事がある場合は別ですが、基本的には「家は仕事をしない場所」と決めています。
「仕事以外の時間」は、何か特別なことをするわけではありませんが、家族とゆっくり過ごしたり、近場へドライブに出かけたりする時間が、私にとって大切なリフレッシュのひとときです。
(取材:2025年3月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。