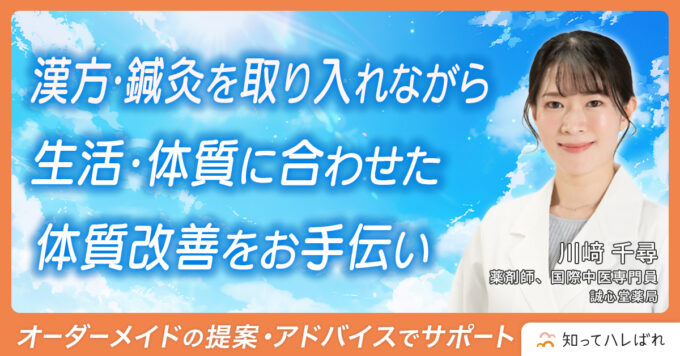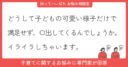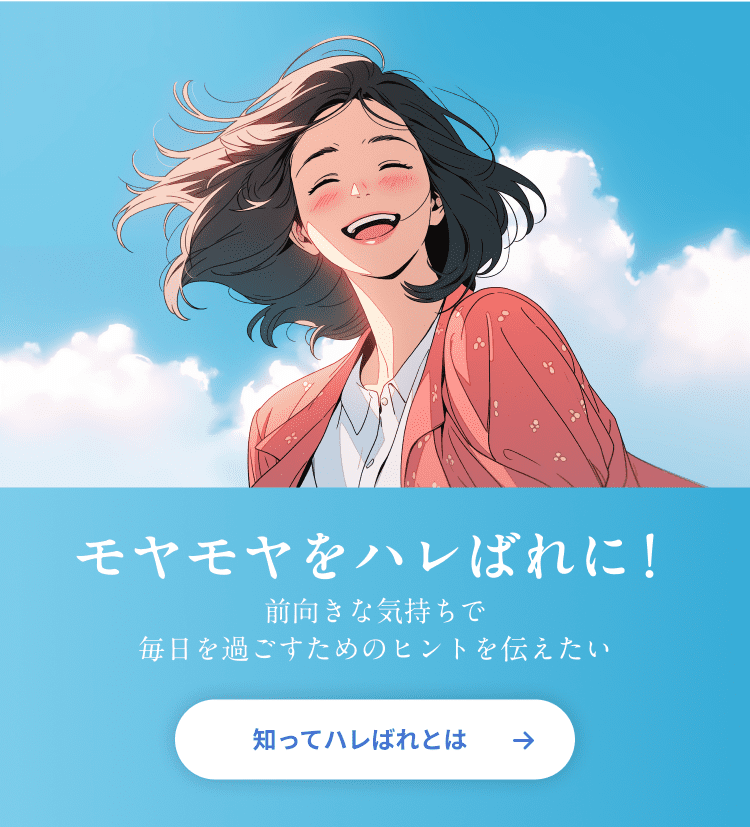女性のライフステージを快適に。婦人科クリニックをもっと気軽に受診して、女性特有の悩みを軽減【医師 奥 久人】

長期的な視点で女性の心と体をサポート
ー奥先生のご経歴と産婦人科を目指した経緯を教えてください
研修医として学んでいた頃、尊敬できる上司と出会ったのが産婦人科医を志すようになったきっかけの一つです。「こんなにすごい人のもとで仕事をしたら、この先何ができるんだろう」と、ワクワクしたことを覚えています。
一般的に医療は「病気を治療する」というイメージが強い中で、産婦人科医は病気を治すことを目的とする以外に、「患者さんの生活の質を上げる」ためのサポートができます。
女性特有の悩みを軽減したり、妊娠や出産など、患者さんのライフサイクルにいろいろな観点から関われることに、大きなやりがいを感じています。
ー月経の改善と子宮内膜症が専門分野とお伺いしました。この分野に注力されるようになったきっかけをお聞かせください
日本国内で低用量ピルが認可されたのは、僕が研修医として勤務していた1999年のことでした。当時はまだ自費処方薬でしたね。月経困難症や子宮内膜症の治療薬として、LEP製剤( 低用量エストロゲン・プロゲステロン)が保険適用となったのは、その9年後の2008年です。
産婦人科医としてスタートした当初、婦人科系の疾患は、「病気が見つかったら手術をする」ことしか治療の選択肢がありませんでした。かつては、子宮内膜症や子宮筋腫の治療も、手術に頼らざるを得なかったのです。
数年後に再発したら、また手術を受けるといった状況では、妊娠を望む頃には子宮も卵巣も大きなダメージを受けてしまいます。
こうした患者さんと向き合う中で、「今すぐ命に関わる病状ではないけれども、生活に支障が出る病気に対して、どうやって治療したらいいのだろう」と考えるようになりました。
5年後、10年後の妊娠に向けて、20年後、30年後に閉経してからも患者さんが自分らしく健康的に過ごすためには、患者さんと相談しながら、長期的なプランニングで治療することが必要です。
こうした観点で考えた結果、「患者さんの生活の質を上げるための治療」をテーマに掲げ、取り組むようになりました。

その後、産婦人科の病院やクリニックで研鑽を重ね、2022年1月に心斎橋駅前に婦人科クリニック「女性クリニック We おおさか」を開業しました。現在は、月経の改善と子宮内膜症を専門分野に掲げ、一人ひとりのライフステージに寄り添えるような診療を心がけています。
低用量ピルが認可されて20年余りが経った今、新薬もどんどん増えています。こうした中で、僕たち産婦人科医ができることは、いかに手術を回避できるか 、病気を発症しないようにできるかをコントロールすることです。
医薬品メーカーや薬剤師の皆さんと協力し、安全な薬を普及させることで病気の発症リスクが抑えられれば、手術はもっと回避できるはずです。さらには、大きな病気を予防することで、妊娠しやすい体調のまま適齢期を迎えることができると思います。
年齢によって異なる生理・PMSの治療法
ー患者さんと接するとき、心がけていることはありますか。
患者さんの気持ちに寄り添い、共感することです。僕は男性なので、本当の意味で共感するのは難しいのですが、患者さんの話を聞いて「そうだね」「大変だよね」と声をかけることを心がけています。
生理・PMS(月経前症候群)のお悩みは、イライラしたり、情緒不安定になったりする精神的な症状から、疲れやだるさ、胸の張り、頭痛・腰痛といった身体的症状など、人によってさまざまです。
患者さんの多くは、ちょっとしたトラブルに悩み、婦人科へ相談にいらっしゃいます。そんな時、医師が正論で答えると患者さんは心を閉ざしてしまうと思うのです。一度婦人科に対する敷居が上がってしまうと、次に困ったことがあっても患者さんは受診を躊躇してしまうかもしれません。
少しでも不安を取り除き、困った時に気軽に婦人科に来ようと思ってもらえる環境づくりを心がけています。


ーどのような年齢層の患者さんが多いのでしょうか
クリニックに来訪する患者さんの年齢層は大きく分けて、25歳前後と40代半ばから50代の2つの世代が多くを占めています。
20代の場合、生理痛やPMSなどを含めて子宮や卵巣のトラブルで受診される方が大半です。若い方は治療方法の選択肢も多く、症状の改善も実感しやすいので、早めに受診されることをおすすめします。
意外と多いのが、生理痛やPMSで悩む40代半ばから50代前半の患者さんです。この年代は、20代、30代の患者さんに比べて提案できる治療や薬の選択肢が少なくなってしまうんですよね。
40歳以上になると、子宮筋腫や卵巣嚢腫や子宮腺筋症など、基礎に病気を持っている人が増える傾向にあります。低用量ピルを使う場合も、年齢が高くなるほど血栓症のリスクが上がります。そのリスクを抑えるタイプの薬を使うと、出血トラブルが増えたり、長期的に継続して使える薬がないなど、40代半ばから50代で使用できる薬の選択肢は現状では少ないのです。

近年ではインターネットやSNSの普及により、ピルや薬についてさまざまな情報をご自身で検索できるようになりました。
しかしながら、その情報を自己流に解釈して、40代〜50代でも、20代と同じ薬が効くと勘違いしてしまう方がいることをとても危惧しています。
先ほどもお話しした通り、低用量ピルには血栓症のリスクがあり、加齢とともに血栓症が発症するリスクは上昇します。50歳以上には禁忌、つまり投与してはいけないとされています。SNSなどの情報を鵜呑みにして自己判断をせず、まずは婦人科を受診してほしいと切に思います。
ー最新は小学生でも月経の悩みやトラブルで受診される方が増えていると聞きましたが。
そうですね。近年、少しずつ患者さんの若年齢化が進んでいると感じます。
これは、栄養状態や生活習慣の変化により、初経の平均年齢が低下していることが一つの要因となっています。それと今の小中学生の母親は、ピルが広く知られるようになった世代が多いこともあり、婦人科を受診して、ピルを飲むことに対する抵抗感も下がっている傾向が見られます。
小中学生は、「辛い生理痛が我慢できない」と訴える患者さんが多いですね。
また、生理痛やPMSの緩和だけではなく、生理周期の安定、試験や旅行に合わせて生理日を調整したいと受診されるケースもあります。ピルを服用することでライフスタイルに合わせて生理を調整できることが情報として広まってきているのかなと感じます。
注意したいのは、10歳未満の場合、ホルモン剤の使用で女性ホルモンの分泌が活発化することによって、成長ホルモンが減少し、骨の成長が鈍化することがあります。まずは婦人科にご相談に来ていただいて、状況次第で大きな病院の小児科を受診していただくこともあります。

ー患者さんとの印象的なエピソードをお聞かせください。
長期的な視点で患者さんと向き合っているため、長いお付き合いの患者さんも多くおられます。
20代の頃に手術をして以来、20年近くも経過を診ている患者さんもいらっしゃって、時にはプライベートな話を聞かせてくれる方もいます。
辛い病状を共に乗り越えて信頼関係を築き、人としてのつながりを持てるひとときが、「いい時間だな」と感じます。
ー生理やPMSで悩む人にメッセージをお願いします。
おりものがいつもと違う、出血量がおかしいなど、なんとなく異変を感じても、「こんな些細なことで婦人科を受診してもいいのかな」と戸惑う方も多いと思います。
しかし、子宮内膜症や子宮筋腫など多くの患者さんと密接に関わってきた経験の中で、その「ちょっとした症状」の背景に疾患が潜んでいたケースを数多くみてきました。
病名がつかない症状は、少しのサポートで改善する場合もあれば、大きな病気を予防することにもなることを、多くの方に知っていただきたいですね。
また、ピルを服用した経験がある方の中には、最初に服用した薬が合わずに、辞めてしまう人もいます。自分に合う、合わないかを決めるのは、3ヶ月飲み続けた結果で判断するのが目安です。
ピルには色々な種類があるため、体質や症状に合わせて服用するものを変えれば、改善する場合もありますので、専門医にご相談ください。
これからも、すべての女性が、自分らしく、快適に過ごすために、もっと気軽に婦人科を受診していただけるような環境を整えていきたいと思っています。

日常の喧騒から離れて1人の時間を大切にする
ー奥先生のリフレッシュ方法を教えてください。
友人と都合が合えばゴルフに行ったり、勤務の合間に薬局でおしゃべりして発散したりもしますが、1人で過ごす時間も大切にしています。
人混みを離れて、海をボーっと眺めたり、競馬場で馬が走るのをボーっと見たり芝生の上で寝転んだり、リラックスできる時間がリフレッシュにつながっています。
1人で飲みに行くのも結構好きですね。自分のペースでお酒を飲みながら、ぼんやりと考え事をしたり、気ままな時間を過ごしていると自然と心が安らぎます。
1人の時間を持つことで自分の考えや気持ちを見つめ直すと、心と体のバランスが整いやすくなりますよ。
(取材:2025年1月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。