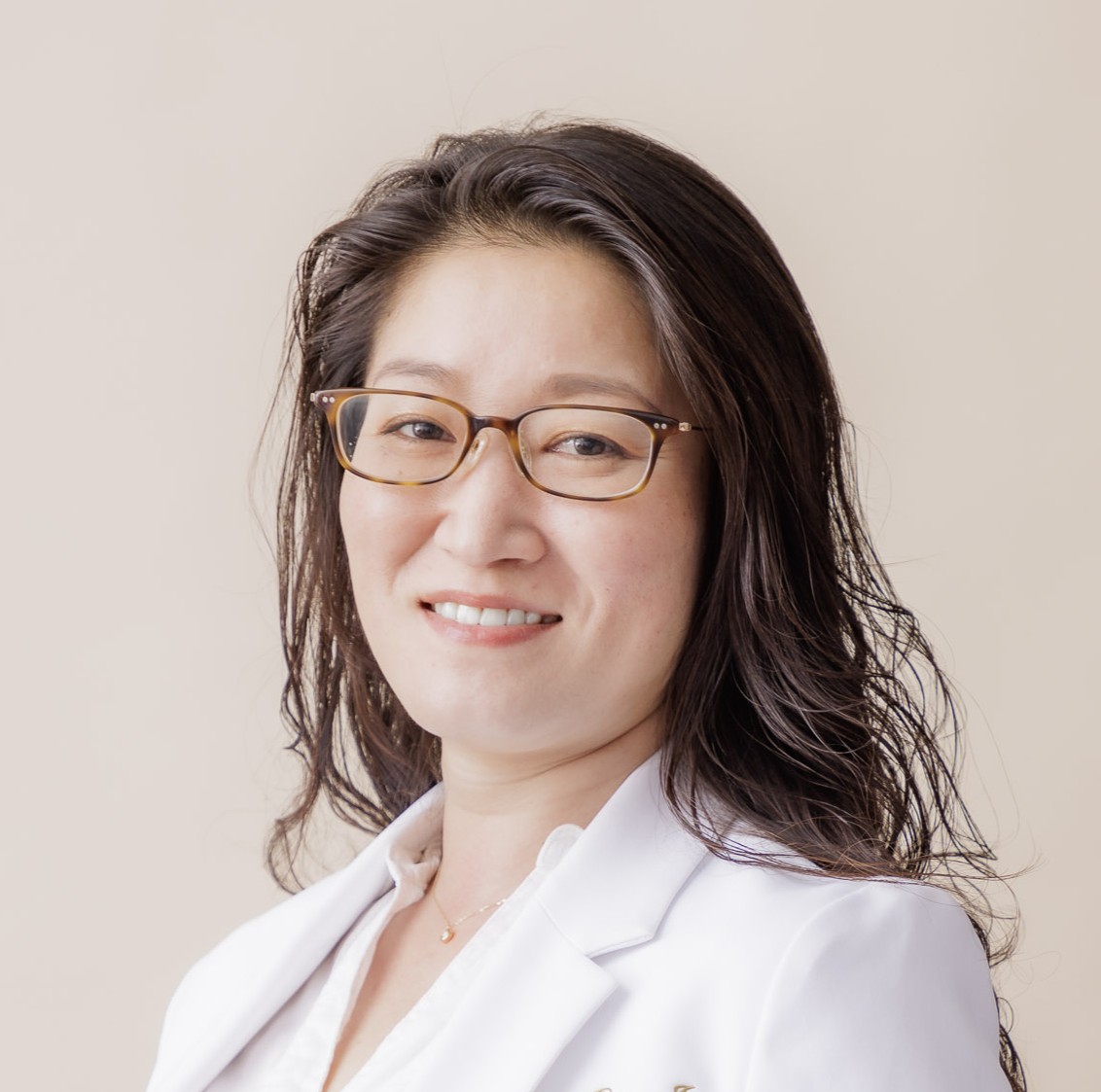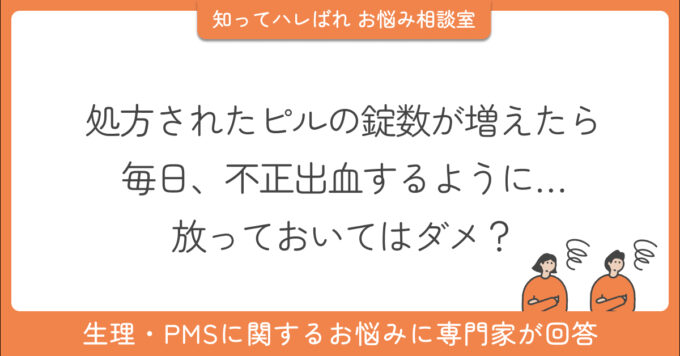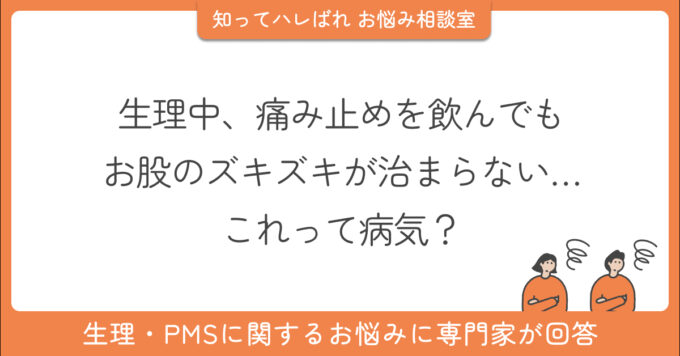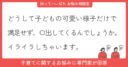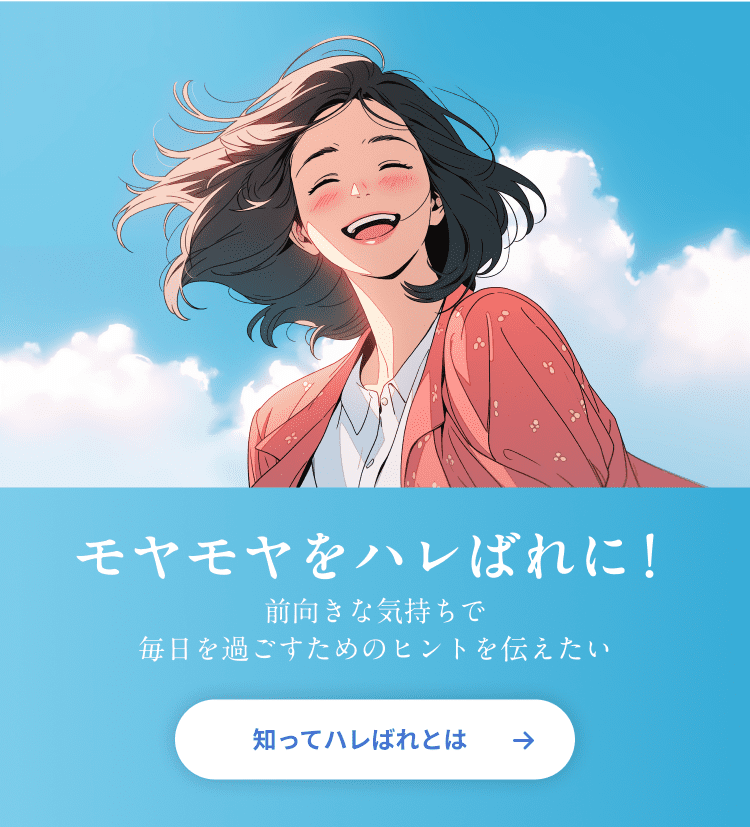PMSで情緒不安定に…不調とどう付き合えばいいかわかりません【お悩み相談室】
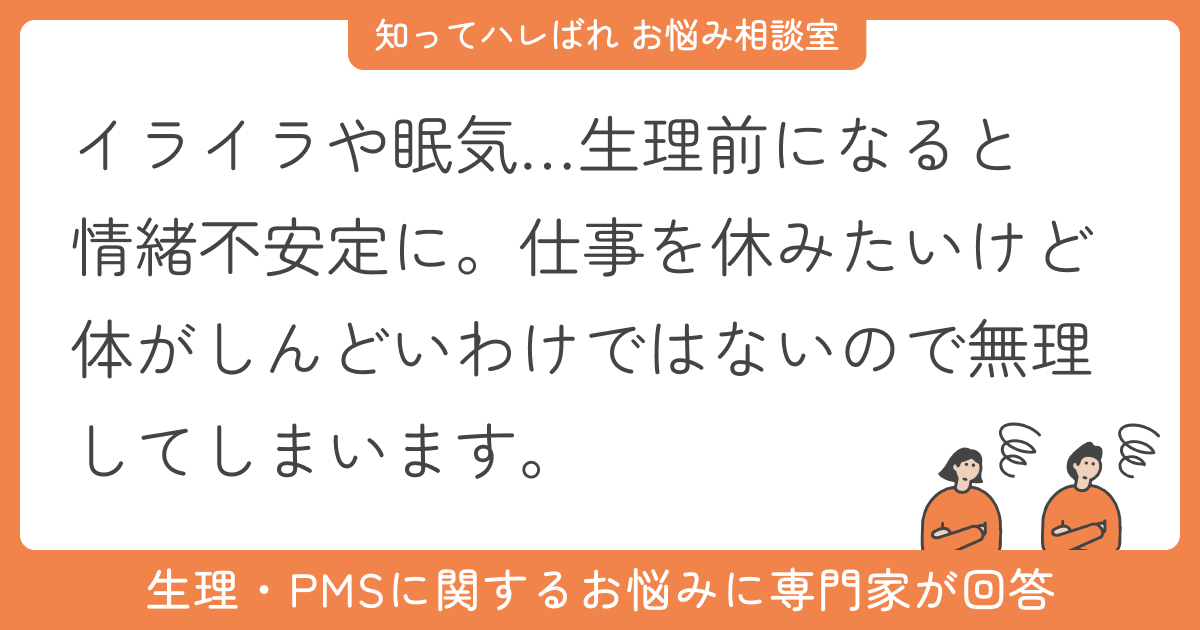
生理前になると気分の落ち込みやイライラがひどく、でも体調不良ではないから休んではいけない…と自分を追い込んでしまう――そんなPMSによるメンタル不調に悩む20代女性からのご相談です。
今回は、PMSやPMDDとの向き合い方、自分を責めずに過ごす工夫について、臨床心理士がお答えします。
PMSによるメンタル不調が辛く、どう乗り越えればよいのか悩んでいます。集中力の低下や強い眠気、イライラが酷く、正直なところ仕事を休みたいと思うこともあります。でも私はお腹が痛いわけではなく、身体的な症状よりも精神的な不調が中心のため、「休んではいけないのでは」と思ってしまい、無理をしてしまいがちです。ピルを服用しているものの、なかなか改善が見られず、不調とどううまく付き合えばいいか分かりません。同じような悩みを持つ方がどのように過ごしているのか、参考になるお話があれば知りたいです。
(20代、女性、ハンドルネーム:もも、職種:事務・オフィスワーク)
目次
最初に
PMSによるメンタル不調、本当におつらいですよね。
人に説明しづらいし、見た目ではわかってもらえないし、かといって何もしていないわけでもない。むしろあなたは、ピルを服用して対処しようとしたり、無理をしながらも仕事をこなしたりと、十分すぎるくらいがんばってこられました。
「身体に症状が出ていれば休めるけれど、メンタルだと休めない」と思ってしまうお気持ち、よくわかります。
でも実際には、メンタルの不調こそ人間にとってダメージが大きく、回復に時間がかかるもの。あなたが「仕事を休みたい」と感じるのは、甘えでも弱さでもなく、「今は休息が必要ですよ」という心のサインなのかもしれません。
そして「同じように悩む人がどうしてるのか知りたい」と思えること――それ自体が、あなたの中に「なんとかこの不調とうまく付き合っていきたい」という前向きな気持ちがある証です。
今まで本当によくひとりで耐えてきましたね。
「不調とうまく付き合う」ってどういうこと?
「不調とうまく付き合う」と聞くと、“無理のない程度に我慢する”みたいなイメージを抱いてしまいがちですが、ここでひとつ考え方の転換をしてみませんか。
本当に目指したいのは、「自分のコンディションに合った暮らし方を知ること」なんです。
つまり、「症状があるけど無理して頑張る」ではなく、「今の私はこういう時期だから、こうやって過ごすのがベスト」と柔軟に過ごし方を選べるようになること。
たとえば、生理前にどうしても感情が不安定になるなら、予定の入れ方を少しゆるくしておく。どうせイライラするなら、ひとりで気楽に過ごせる時間を確保する。
集中できないときは、「仕事に向いてないんじゃなくて、今日は生理前だったわ」と気づいて、少しタスクの負荷を調整する――そんな感じで、「不調の波に飲まれない過ごし方」を少しずつ積み重ねていけるといいですね。
そして、必要なら「月に一度、休む日があってもいい」と自分に許可を出すことも、立派なセルフケアです。
メンタル不調との付き合うための3つの視点
PMSの中でも精神的な不調が強く出る状態は「PMDD(月経前不快気分障害)(※)」と診断されることがあります。これは一時的な気のせいではなく、医学的にも認められている症状です。
精神的な不調をケアする視点として、以下の3つを参考にしてみてください。
1. 周期の把握と“見える化”
症状日誌(症状の頻度,発症時期,重症度)をつけることで、自分のメンタルや集中力のパターンが見えてきます。今ではスマホのアプリでも手軽に記録できます。
「今月もきたか」と分かるだけでも、安心感が違ってきます。
2. 自分を許す“逃げ道”を持つ
強い眠気やイライラは、自分でもどうしようもないことがあります。そのときに、自分を「ダメな人間」と責めてしまうとさらに悪化します。
むしろ「今日は低気圧とPMSがタッグを組んでいるから最強」など、ユーモアを交えて、自分を許す「逃げ道」を作る視点が役立ちます。
3. 専門家に“相談する自分”もメンタルケアの一部
ピルは効果が出るまでに個人差があり、合う種類に出会うまで時間がかかることもあります。婦人科だけでなく、メンタル不調が強い場合は心療内科や精神科の医師、または臨床心理士など心理職にも相談してみましょう。
特に仕事の継続や日常生活に支障が出ている場合は、対人関係や職場での調整も視野に入れた対応が必要になることもあります。
心療内科や精神科と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、中等症~重症の PMS・PMDD に対して、気分を安定させるお薬を使うことは、PMS・PMDDの治療ガイドライン(※)にもはっきり書かれているのですよ。
最後に
大切なのは、「我慢して乗り越える」ではなく、「ちゃんと休んで、助けを求めて、乗り切っていく」こと。
このコラムを読んでいるあなたが、ほんの少しでも「私ひとりじゃないかも」と思えたら、そこからが回復の第一歩です。
<参考文献・出典>※以下の文献を参考にしています
公益社団法人 日本産科婦人科学会
▶「PMS・PMDDの診療と治療」ガイドライン:https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/PMS_PMDDshishin.pdf
専門家がこたえます!お悩み募集中です
「知ってハレばれ お悩み相談室」にお悩みをお寄せください。
毎月ピックアップさせていただいたお悩みとその回答を、「知ってハレばれ お悩み相談室」の記事で公開いたします。下記のフォームからお悩みをお寄せください(匿名でお寄せいただけます)。