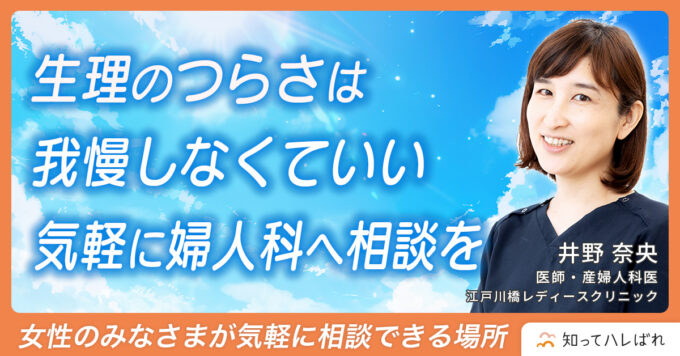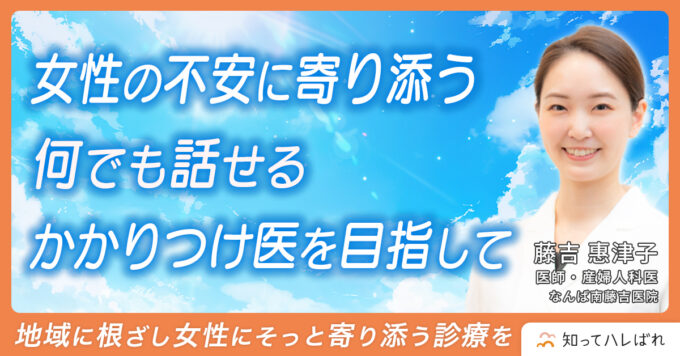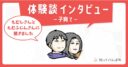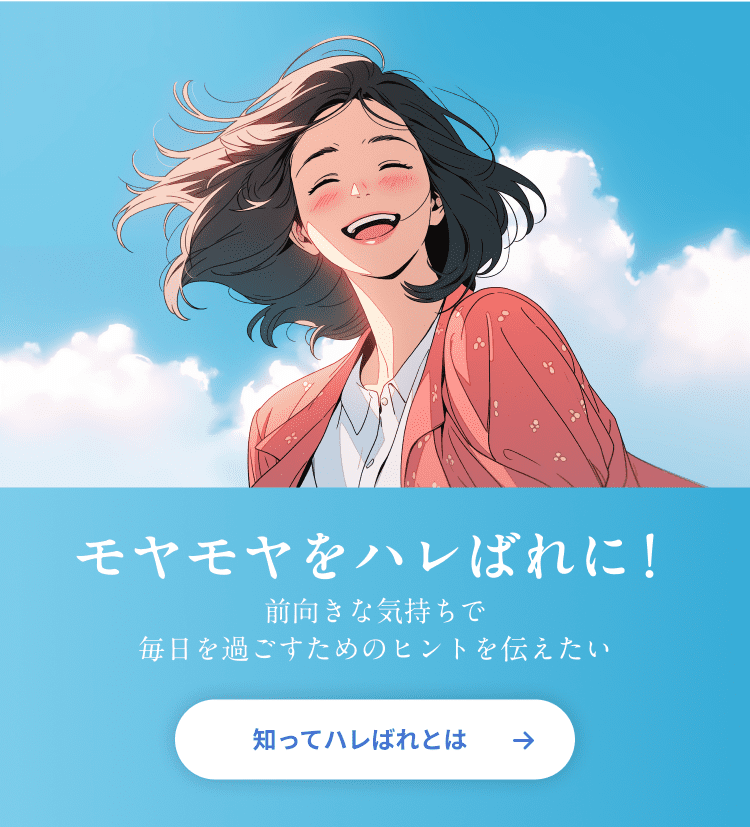月経周期にまつわる心身の不調は、まずは婦人科へ気軽にご相談を【医師 宮島 慎介】
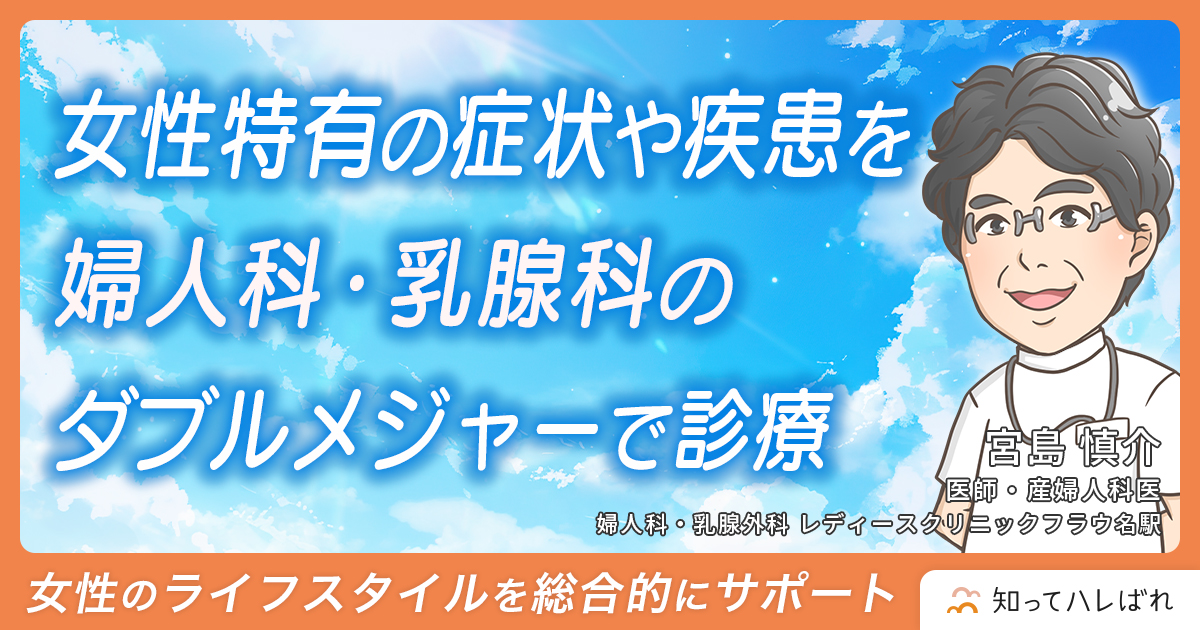
目次
「婦人科」と「乳腺科」ふたつの専門性で婦人科疾患をトータルにサポート
――宮島先生が医師を志したきっかけを教えてください
私の両親は医師の家系というわけではありませんが、親族にひとり医師がいて、私自身、子どもの頃からその方と親しくしていました。そのため、医療という仕事が自然と身近に感じられる環境でした。
また、高校時代には母が病気で入院したことがあり、その経験が医師を目指す大きなきっかけになっています。
――産婦人科から外科(乳腺外科)へと転向された経緯を教えてください
産婦人科を選んだ理由は、「お産が好きだから」という先生が多いと思いますが、私の場合はどちらかというと、もともと手術への関心が強く、研修医時代も外科に進むか産婦人科に進むかで迷っていました。
最終的に婦人科を選んだのは、診断から検査、手術まで一貫して自分で関われる点に魅力を感じたからです。外科では、たとえば大腸がんであれば内科が診断し、手術は外科が担当するという分業体制が一般的ですが、婦人科では自分で診断をつけ、治療まで進めることができます。また、手術だけでなく、ホルモン療法など内科的な治療にも携われる点も大きな魅力でした。
大学卒業後は、産婦人科医として6〜7年勤務しましたが、外科への思いをどうしても諦めきれず。婦人科の専門医を取得したタイミングで一般外科に入り直し、もう一度初期研修から学び直しました。
その時点では乳腺外科を志していたわけではなく、まずはさまざまな外科手術を経験したいという思いで取り組んでいました。
一般外科の初期研修の最後には、大腸外科なのか、消化器外科なのか、それとも胸部外科か心臓外科かといった、いずれかの専門を選択する必要があります。さまざまな分野を経験するなかで、自分が持っている産婦人科の知識が「乳腺外科」で活かせると気づき、この分野に進むことになったという経緯です。

(https://www.clinic-frau-sakae.com/)
女性特有の不調や疾患をトータルで支えられる唯一無二の体制
――クリニックはどのような思いから開業されたのでしょうか
私がクリニックを開業したのは2016年のことです。当時、名古屋近郊には乳腺外科を専門とするクリニックがほとんどありませんでした。大学病院で乳腺外科の外来を担当していた時には、朝9時から夜9時まで、休憩も取れずに診察が続くという、完全にパンク状態の日々が続いていました。
そんな中で、「せめてファーストタッチの診断だけでも、地域の中で担える先生がいれば…」と感じるようになり、そこから開業という選択肢を現実的に考えるようになったのが、ひとつのきっかけです。

開院にあたっては、乳腺外科だけでなく、自分のこれまでのキャリアを活かした診療スタイルにしたいという思いがありました。特に、女性のみを診察する立場だからこそ、婦人科と乳腺外科の両方に対応できることは大きな強みになると考えました。
それまでの経験からも、乳腺の不調と婦人科的な症状を同時に抱えている方は多く、「実は乳房の痛みも気になっていて」といったご相談は、婦人科でも乳腺外科でもよくいただいていました。そうしたときに、「それは別の科で診てもらってください」とお伝えするのではなく、ひとつのクリニックでトータルに診られる体制が理想だと考えるようになりました。
欧米、たとえばドイツでは、産婦人科医が乳がんの診断や治療まで担っているケースもあります。私自身も乳腺外科を経験すればするほど、そうしたスタイルで診療できる医師でありたいという思いが強くなり、「婦人科」と「乳腺外科」の両方を専門として掲げるクリニックとして開院することにしました。
ちなみに、クリニック名の「フラウ」は、ドイツ語で「女性」という意味です。女性の健康をトータルで診るというドイツの医療体制に共感し、ドイツ語を引用して「フラウ」という言葉をクリニック名にしました。

――クリニックの特長や強みを教えてください
当院の一番の特徴は、やはり「婦人科」と「乳腺外科」の両方を専門とする医師が診療している点にあります。
全国的に見て、乳腺外科と婦人科の専門医がそれぞれ在籍している施設は少しずつ増えてきていますが、ひとりの医師がどちらも専門として診療を行っているクリニックは、非常に珍しい存在だと思います。まさに“唯一無二”と言えるような体制が、当院の強みです。
特に、乳がんの術後にホルモン療法を受けている患者さんなどは、治療の影響で不正出血が起こることもあります。こうしたケースでは、乳腺外科だけでも婦人科だけでも対応が難しくなる場面がありますが、両方の知見を持っていることで、患者さんにとって最適なアドバイスや治療方針を総合的にご案内できると自負しています。


患者さんにしっかり寄り添いながら、根拠に基づいた医療を実践
――患者さんと向き合う中で大切にしていることや心がけていることはありますか
患者さんと向き合ううえで大切にしているのは、「EBM(Evidence Based Medicine)」、つまり根拠に基づいた医療を実践することです。あまりに個人的な考えに偏った診療にはしたくない、という思いがあります。
これまでにも、他院での診療内容について「これは本当に正しいのだろうか」と感じるケースをいくつも見てきました。もちろん、医師も人間ですし、診断や治療のスタイルに多少の違いがあるのは自然なことだと思います。
ただ、現在はアメリカをはじめ、さまざまな国でガイドラインが整備され、どの医師が診ても大きくブレない、文献に基づいた治療方針が示されるようになってきました。内科をはじめ、ほとんどの診療領域でこの20年ほどの間にそうした基準がしっかりと整ってきています。私自身も、そうしたガイドラインを軸に、ブレない診療を心がけています。
一方で、EBMだけに偏りすぎるのではなく、「医術は人術」という言葉があるように、その方その方の症状や背景にきちんと寄り添うことも大切にしています。痛みやつらさをできる限り取り除けるよう、丁寧にお話を伺いながら、その人に合った治療をご提案することを常に意識しています。


――医師としてのやりがいを教えてください
医師としてのやりがいは、やはり患者さんからいただく「ありがとう」の一言に尽きると思います。手術をした患者さんから「助けてもらって、本当に感謝しています」といった言葉をいただけると、それだけで「この仕事をやっていてよかった」と心から感じます。
医師に限らず、サービスを提供する立場にある方であれば共通する部分かもしれませんが、やはり誰かの役に立てたと実感できる瞬間というのは、大きなやりがいにつながっています。
――生理やPMSでお悩みの患者さんについてどのようなタイミングで受診されるのでしょうか
生理やPMSに関するご相談は、非常に多くいただいています。当院ではそれに加えて、更年期障害に関するご質問やご相談も多く寄せられます。
特に多いのは30代から40代の方で、「これはPMSなのか、それとも更年期の始まりなのか」といった判断が難しい症状について、初診の段階でご相談をいただくこともよくあります。このように、ライフステージが変わり始める時期だからこそ、不安や疑問を抱えて受診される方が多い印象です。

――月経にまつわる症状で乳腺に関連するものはあるのでしょうか
月経があるということは、その背景に排卵があることが多く、月経周期に伴ってホルモン分泌量の変動があります。女性ホルモンは卵巣から分泌されますが、乳腺はそのホルモンの影響を受ける部位のひとつです。
とくに月経前には乳房の張りや痛みを訴える方は多くいらっしゃいます。
現在のところ、乳房の張りや痛みに対して保険適用となるような治療薬は存在しませんが、生活に支障が出るほど強い症状がある場合には、排卵を抑えることで乳腺の症状を軽減できるケースもあります。これはPMS(月経前症候群)に対する治療と似たアプローチで、患者さん一人ひとりの状態に応じて対応するようにしています。
――ちなみに乳腺に関わるトラブルで気をつけたい症状はありますか
受診のきっかけとして多い乳腺のトラブルは、「しこり」ではなく「痛み」です。意外に思われるかもしれませんが、実際には「しこりはないけれど痛みがある」という症状で受診される方が非常に多くいらっしゃいます。
一方で、乳がんのケースは、痛みがあるよりもしこりがある場合に多く見つかる印象です。つまり、「痛みのないしこり」こそ注意が必要だと言えます。しこりといっても、見た目で分かるほど大きく腫れることは少なく、触れてみてはじめて気づくものです。
そのため、日ごろから乳房に触れて変化を確認する習慣をもつことが大切です。いわゆる自己検診とまではいかなくても、「最近ちょっと違うかな」と気づけるきっかけになります。

――読者へのメッセージをお願いします
PMSはさまざまな症状があり、更年期障害に似た全身の不調が現れることもあります。下腹部だけではなく、胸の痛みや頭痛、メンタル面の不調などなど、本当に多岐にわたります。
月経の周期に関連して、毎月でなくても同じ時期に何か気になる症状がある場合は、遠慮なくご相談ください。婦人科に関わる関わらないは関係なく、どんな些細なことでも気軽に話してほしいとお伝えしたいですね。
サウナや銭湯で心身ともにリフレッシュ
――先生ご自身のリフレッシュ方法を教えてください
そうですね、気分をスッキリさせるためにサウナや銭湯に行くことが多いですね。
サウナでととのったり、広いお風呂に入ったりすることで心身ともにリラックスでき、疲れがとれてリフレッシュできます。忙しい毎日の中でも、こうした時間を持つことはとても大切だと感じています。
(取材:2025年5月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。