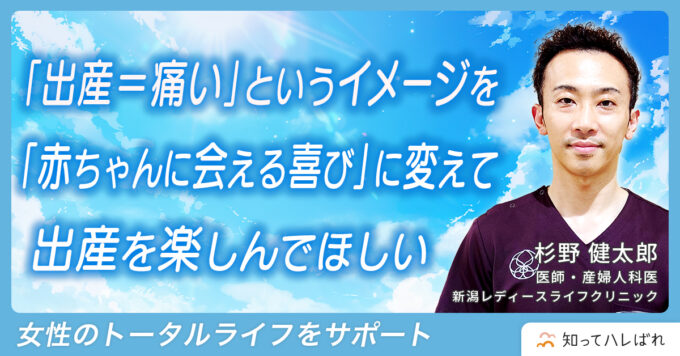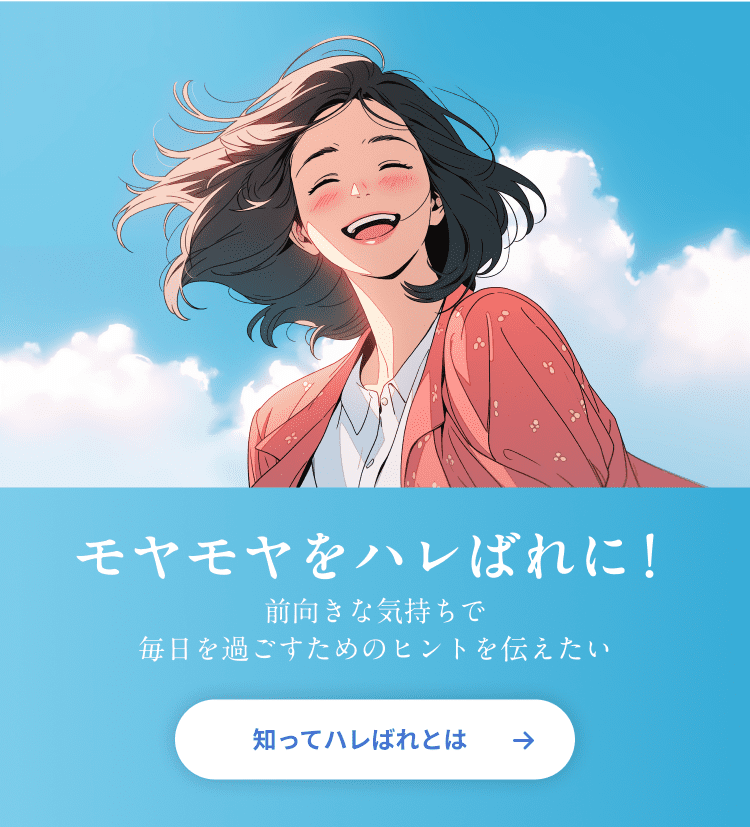自然分娩を基本に、妊婦さんが望むお産のカタチを尊重します【医師 藤東 淳也】
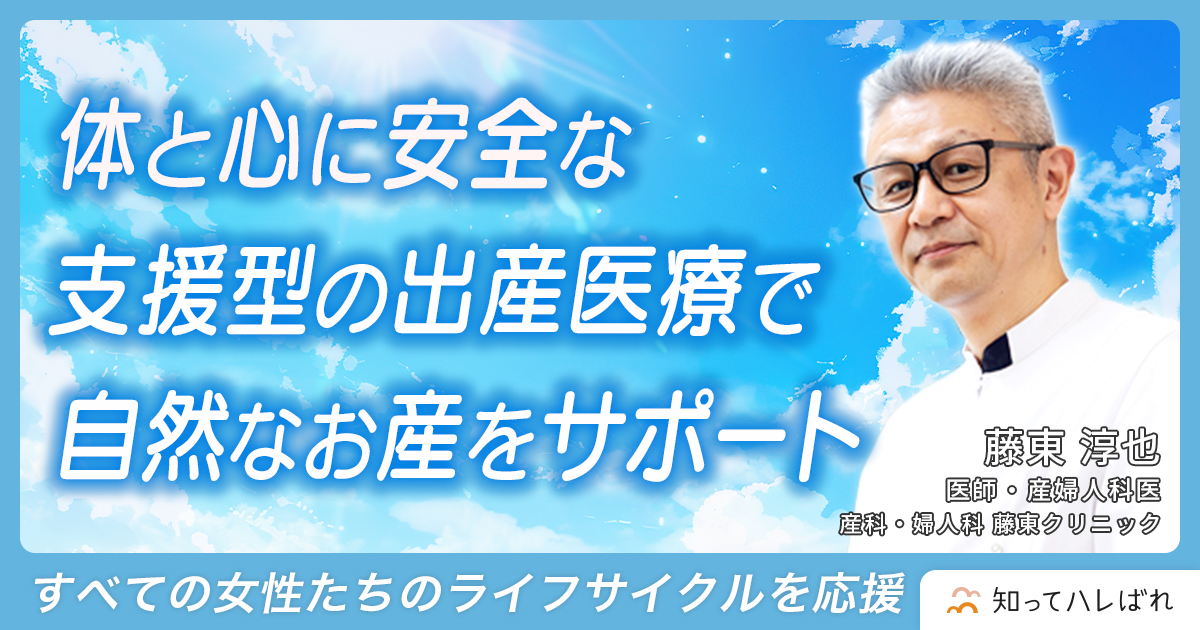
目次
3代続くクリニックを受け継ぎ、地域の産科医療に貢献
―藤東先生が産婦人科医を志したきっかけを教えてください
産婦人科医を目指したのは、私にとって自然な選択だったと思います。祖父の代から開業医の家系で、父が院長をしているときも、1・2階がクリニック、3階が自宅という環境で育ちました。
ひと昔前の産婦人科の開業医といえば、院長が1人ですべてを担当するスタイルが一般的で、昼夜を問わず、懸命に産婦人科医の使命を全うする父の背中をいつも見ていました。
忙しさの中にも、父の嬉しそうな姿や、やりがいをとても身近に感じ、命が誕生する場を支える仕事の素晴らしさを誇らしく思っていたのです。
東京医科大学医学部に進学し、都内の大学病院や総合病院で研鑽を重ねた後に広島に戻りました。県立広島病院の婦人科部長を経て、実家のクリニックを引き継ぎました。現在は副院長を務める弟をはじめ、他の医師や助産師、看護師など、約60名のスタッフと協力しながら、チームで女性のトータルライフを支えています。

心地良い空間づくりで親しみやすいクリニックを目指す
―とても開放的な雰囲気のクリニックですが、空間づくりのこだわりをお聞かせください
やはり婦人科というのは、今でも「なかなか気軽に受診しづらい」というイメージが強いですよね。だからこそ、気軽に通ってもらいやすい、親しみやすい空間づくりを目指そうと思いました。
15年前に先代から世代交代したのを機に現在の場所に移転し、クリニックの建て替えをおこないました。大切にしたテーマは「心安らぐ空間」と「オープンな環境づくり」です。
1階の待合室は大きな窓に囲まれていて、陽の光を取り込んだ明るい室内で、ゆったりとくつろぎながら待ち時間を過ごしていただけるようにしています。外からも待合室の様子を見ることができる開放的な空間です。
当初はあまりにもオープンなので、外からの視線に抵抗のある患者さんもいらっしゃるのではないかと心配していましたが、患者さんからは「開放的で気持ちがいい」という言葉をいただくことも多いですね。
院内の廊下などにいると、入院している患者さんの姿も外から見えてしまうのですが、たとえ入院中であっても「人から見られている」という意識を持つことは大切なことなのでしょう。みなさんが身だしなみに気をつかわれたり、ハツラツと過ごしている様子を目にすると、良い相乗効果が生まれていると感じます。


―現在、地方では分娩可能なクリニックが減少しています。こうした中で、クリニックを守り続けることへの思いをお聞かせください
そうですね、産院を必要としてくださる方がいる限り、その声に応えていくことが私たちの使命だと考えています。
分娩に関して、世界的に見たときに日本は実は特殊な文化をもっています。いわゆる「産院」と呼ばれる分娩も扱う小規模な施設で出産するという形は、先進国では日本だけです。
たとえばアメリカでは、妊婦健診は近隣のファミリークリニックに通い、日本の総合病院よりもさらに大きな規模の病院で出産するのが標準的なスタイルです。先進国の多くはこのような体制をとっていて、出産施設としての「産院」というものが残っているのは珍しいことです。
実際に調べてみても、日本のこうした状況は40〜50年前から大きくは変わっていません。総合病院などの医療機関で出産する方と、いわゆる産院のような施設で行う方とで、だいたい半々くらいの割合がずっと続いています。出産に対する日本人ならではの価値観や考え方が根強くあり、産院へのニーズが今も一定数あるということだと思います。
また、日本ではハイリスク妊婦・分娩への対応やNICU(新生児集中治療管理室)を有する、周産期センター(周産期母子医療センター)がしっかりと機能を果たしています。私たちのような産院施設がやっていけるのも、そういったセンターとの連携があるからこそです。
何か少しでも異常が疑われれば、すぐに周産期センターに移ることができる、日本はその連携体制が非常に優れていて、小規模な施設で出産される方が半数を占めているにも関わらず、周産期死亡率の低さは世界トップクラスです。こうした分業と連携が、日本の産科医療の強みだと思っています。
こうしたなか、当院は、単にお産を扱うだけでなく、妊婦さんの体と心のケアにも力を入れており、「快適で安全なお産」を支えるきめ細やかな医療を提供しています。もちろん、クリニックを続けていくためには少子化問題などさまざまな課題もありますが、必要としてくださる方がいる限り、地域の分娩施設を維持していきたいと考えています。

女性の一生に寄り添える“かかりつけ医”でありたい
―女性のトータルライフを支える医師として、どのような思いで患者さんと向き合っていますか
そうですね。女性の体は、ホルモンの変化や月経、妊娠・出産など、ライフステージごとに本当にさまざまな変化があります。そして今の女性は、仕事と家庭の両方で多くの役割を担い、非常に忙しくされているため、心身のバランスを崩しやすいのも当然だと思います。
そうした心身の不調や悩みに、少しでも医療の側から手を差し伸べることで、心や体が軽くなり、生活全体が前向きに変わることもあります。そういう小さな変化の積み重ねが、女性の方々の暮らしをより豊かにできるのではないかと私は感じています。
当院のコンセプトのひとつに「女性の生涯に寄り添う」というものがあります。妊娠や出産といった特別な時期だけでなく、妊娠の前段階から体調を整えること、また出産後のケアまで、すべての時期においてサポートが必要だと考えています。
実際、妊娠してから慌てて相談に来られる方も多いのですが、本当はその前の準備や体調管理がとても大切です。妊娠・出産は一時的な出来事ではなく、女性の人生に深く関わるプロセスの一部だと考えます。
妊娠中という限られた期間だけ体を気遣うのではなく、妊娠に備えて体調管理をすること、加齢と共に適切なケアが必要であることを一人でも多くの女性に知ってほしいと思っています。
どのステージにいる女性に対しても、その時々の不調や不安に寄り添いながら、一緒により良い方向を考えていくような診療を心がけています。少しでも安心して過ごしていただけるよう、お力になれたらうれしいですね。


―日々の診療の中で、やりがいを感じるのはどんな時ですか。
当院では、年間およそ800人ほどの赤ちゃんが生まれています。やはり、無事にお産を終えられて、患者さんとご家族の喜んでいる姿を見る時が嬉しいですね。
また、長くこの地域で診療を続けていることもあり、二世代、三世代にわたって通ってくださるご家族もいらっしゃいます。たとえば、親子で受診されて「私もこの子もここで生まれたんですよ」と話してくださることがあって、本当にありがたいなと感じます。そうした地域とのつながりや、信頼関係の積み重ねが、この仕事の大きなやりがいになっています。
一人ひとりが思い描く理想の出産を支援
―藤東クリニックが実践している「支援型」の出産について教えてください
先ほどもお話ししたように、日本の産科医療は、「管理型」と「支援型」の二極化が特徴です。たとえば総合病院や周産期センターなどは「管理型」の医療を担っており、重症な妊婦さんや合併症のある方などに対して、医療的にしっかりと管理を行うことが求められています。これはもちろん必要不可欠な存在で、医療の安全を支える非常に重要な役割を果たしています。
一方で、私たちのような「支援型」の産科医療では、一人ひとりの思いや希望を尊重しながらお産を迎えられるようにサポートしています。
たとえば「出産後すぐに赤ちゃんを抱っこしたい」「自分でへその緒を切ってみたい」といったバースプランを事前に伺って、できる限りご希望に沿った形でお手伝いするようにしています。ご家族の思いを実現できるよう、一緒に考えながらお産を組み立てていくことも支援型の魅力のひとつだと感じています。
出産は、一人として同じかたちはありません。それぞれの方が、それぞれの想いをもって迎える大切な瞬間です。その気持ちに丁寧に寄り添いながら、「その方らしいお産」をサポートしていけることを、私たちはとても大切にしています。

―助産師が担当する「助産外来」では、どのようなことを行っていますか
当院では助産師にゆっくり悩み相談ができる「助産外来」を設けています。
患者さんにとって、ささいな相談を持ちかけることは勇気がいることだと思います。通常の妊婦健診では、躊躇や遠慮もあって、なかなか聞きたいことや不安に思っていることを話しきれないこともあるでしょう。
助産外来では、助産師と1対1でじっくり話す時間を設けていますので、「ちょっと気になるな」というような小さな違和感や不安も、安心してお話しいただけます。実は、そうした“ちょっとしたこと”って、とても大事なんですよね。そこに早く気づけることで、安心につながったり、大きなトラブルを未然に防げたりすることもあります。
妊娠は本当にスピード感のある変化の連続です。受精卵というたった1つの細胞が、10ヶ月という短い期間で赤ちゃんになるという、まさに奇跡のようなプロセスです。その過程の中では、少しの違和感でも見逃さないことがとても大切になります。
だからこそ、患者さんが感じるちょっとした違和感や不調は、私達にとって貴重な情報源だと思っています。安全な出産を迎えていただくために、「小さな変化を見逃さない」ことを大切にしたいのです。
そして、悩みを打ち明けることで出産に対する不安を解消し、穏やかな気持ちで妊娠期間を過ごしていただけるよう、サポートしたいと考えています。
―家族と一緒に味わえる「御祝会席」をはじめ、病院食にこだわっているそうですね
そうですね。出産というのは本当に大変なことですし、その後すぐに赤ちゃんのお世話が始まります。せめて入院中の数日間というのは、少しでもほっとできる時間であってほしいと願っています。
特に、食事は入院生活の中でも大きな楽しみのひとつですから、できるだけ美味しく、そして気持ちが明るくなるような内容にしたいと思っています。
私たちのクリニックでは、お産を頑張ったお母さんへのねぎらいの気持ちを込めて、特別な御祝会席をご用意しています。ご家族と一緒に召し上がっていただけるようにしているのも、新しい命の誕生をみんなで喜び合える、幸せなひとときになってほしいという願いからです。
せっかく頑張って赤ちゃんを産んでくださった方々に、少しでも「ここで良かった」と感じていただけるよう、私たちにできることをひとつずつ丁寧に届けていきたいと考えています。

四季旬彩を生かした料理でおもてなし
―出産にはスタッフのチームワークも大切だと思います。働きやすい環境を整えるために、工夫されていることはありますか
そうですね。うちはそれほど大きな施設ではないので、スタッフ同士の距離がとても近いというのが特徴です。看護師や助産師を含め、全体で60人ほどの規模ですので、顔の見える関係が自然と築かれていて、部署を越えての連携もしっかりできています。
外来に来ていた患者さんが入院されても、顔なじみのスタッフがいるという安心感がありますし、患者さんとの距離も自然と近くなるのは、うちならではの良さだと思っています。
また、スタッフ自身のライフステージも大切にしていて、妊娠・出産を経験するスタッフも多いので、産休や育休はもちろん、復帰後の働き方にも柔軟に対応できるようにしています。たとえば勤務時間を短縮したり、無理のない範囲でシフトに入ってもらったりと、できるだけ長く、安心して働ける環境を整えています。
スタッフが安心して働けてこそ、患者さんに対してもより良いケアが提供できると考えていますので、制度面も含めてしっかりと支えていけるよう取り組んでいます。
妊娠・出産は奇跡のようなできごと、自信と誇りを持って楽しんでほしい
―これから出産を考えている方や妊娠中の方にメッセージをお願いします
妊娠というのは、本来とても素晴らしいことです。たった一つの細胞が、わずか10ヶ月の間に30兆個もの細胞に成長し、赤ちゃんとして誕生する。これは奇跡のようなことです。
今、日本では出生数が減少し、少子化が深刻化しています。このような状況の中で、「妊娠・出産は大変そう」「育児は辛いもの」というような、どちらかというとネガティブなイメージが広がっているように感じます。妊娠していることを楽しんだり、幸せを感じたりすることに、どこか遠慮してしまうような雰囲気があるのは少し寂しいことですよね。
妊娠や出産、子育ては本来、とても楽しくて喜びに満ちたものです。数十年前までは、妊娠することそのものが希望に満ちていて、家族やまわりの人たちと一緒に喜びを分かち合う時間でもありました。
どうか、ご自身の妊娠という経験、「新しい命を育んでいる」という事実にもっと自信と誇りを持ってください。妊娠・出産は決して「我慢するもの」ではなく、楽しみながら迎えていいものです。そして、そう感じられる社会であってほしいと、私たち医療者も願っています。

―最後に藤東先生のリフレッシュ方法を教えてください
ちょっと行き詰った時には、歩くようにしています。いろいろな問題を考えながら散歩していると気分転換になり、解決策が見つかることもあります。
とりあえず歩いていると、自然に心と体がほぐれ、違う視点から物事を見られるようになりますよ。
(取材:2025年5月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。