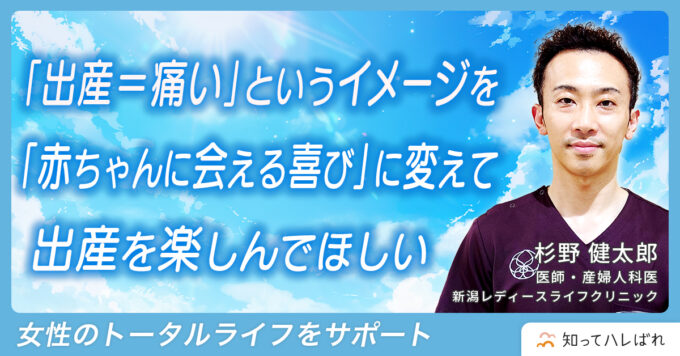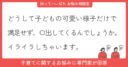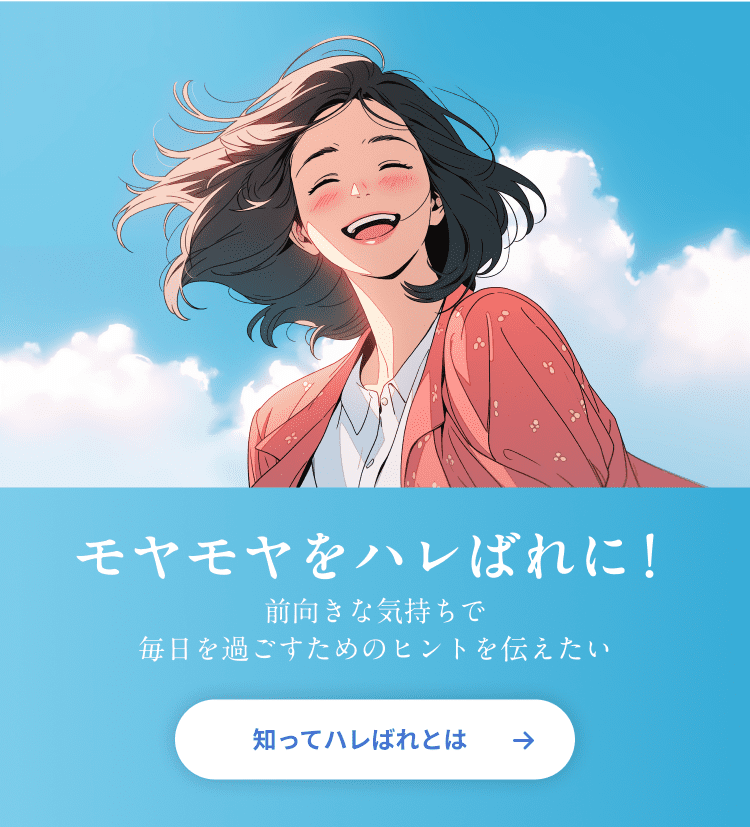「生まれる前から」守り抜く、出生前検査から分娩までトータルで支える、地域に根ざした産婦人科医療【医師 宮崎 顕】

photo by Toshihisa Ishii(Blitz STUDIO)
目次
祖父の代から続く地域に根ざした産婦人科クリニック
――宮崎先生が産婦人科医を志した理由をお聞かせください
当院は、三重県の鈴鹿の地に、祖父の代から70年以上続いているクリニックです。祖父も父も医師だったため、小さな頃から医療は身近な存在でした。進路にすごく悩んで医師になったというよりは、自然と医師を目指していたという方が近いかもしれませんね。
ただ、最初から「産婦人科医」になろうと決めていたわけではありませんでした。医学部に進学した当初は手術などを行う外科系に進みたいと考えていて、その中でも特に、診断から治療、その後の経過までを一貫して見届けられる科に興味がありました。
整形外科も迷ったのですが、最終的に選んだのが産婦人科でした。今では、母体と胎児を守る医師として自分のやりたいことも見つかっているので、この道を選んで結果的に良かったなと思っています。
――地方で産科を扱うクリニックは貴重ですよね。地域に根ざした産婦人科クリニックとして、どのような思いをお持ちですか
現在は、僕が産科を専門とし、副院長である妻が思春期から更年期までの女性のあらゆる悩みに対応する女性医学(婦人科)を専門としています。弟である純医師も含めて、皆があらゆる産婦人科疾患に対応し、女性の幅広い診療ニーズにお応えできるよう互いに専門分野を分担・連携しながら診療にあたっています。
産科と婦人科の両面からトータルでサポートすることで、地域にお住まいの女性の皆様に長く寄り添い、安心していただける医療を提供していきたいですね。
――クリニックのロゴマークが特徴的ですが、どのような意味が込められているのでしょうか
実は、このロゴマークには「これ」と決めた特定の意味はないのです。見る人によって、いろいろな捉え方ができるようにデザインしています。
多くの方は赤ちゃんの姿に見えると言われますし、花のようだとおっしゃる方もいます。円の組み合わせで形づくられているのですが、「その人が、その時に感じたイメージがそのまま答えになる」、そんな余白を持ったロゴであればいいなと思っています。

https://www.miyazaki-clinic.jp/
患者さんとスタッフ、双方への心配りを大切に
――日々の診療の中で、特に大切にされていることや、患者さんと向き合う際に心がけていることはありますか
ありきたりな言葉になってしまうかもしれませんが、まずは患者さんのお話をしっかりと伺い、ご質問には真摯にお答えすることです。そして、少しでも満足して帰っていただくことを大切にしています。
「産婦人科を受診する」ということは、女性にとって非常に不安なことですし、時には勇気がいることだと思います。だからこそ、すべての患者さんやご家族が安心・リラックスして、納得のいく医療を受けていただけるよう心がけています。
患者さんが「何を伝えたいのか」をしっかりと汲み取り、できる限りその想いに応えていきたいですね。気持ちとしては、いつでも頼っていただけるよう「24時間いつでも対応しますよ」というスタンスで日々の診療に向き合っています。
――「先生はもちろん、スタッフの皆さんもやさしい」というクチコミを多く拝見しました
自宅がクリニックと同じ建物内にありますので、緊急の帝王切開などが必要な場合でも、24時間いつでも迅速に対応できる体制を整えています。時間や曜日を問わず柔軟に動ける点は、当院ならではの手厚いサポート体制だと自負しています。
また、患者さんに喜んでいただくことはもちろんですが、それと同じくらい、スタッフの働きやすさも大切にしています。スタッフ自身が気持ちよく働けていないと、その雰囲気はどうしても患者さんに伝わってしまいますからね。患者さんに対してもスタッフに対しても、同じように心を配ることを大切にしています。


医師としての分岐点、「胎児治療」との出会いがライフワークへ
――先生がこれまで医師として、特にやりがいを感じた出来事や、印象に残っているエピソードがあれば教えていただけますか
医師としての大きな分岐点となり、現在の診療方針につながった印象的な出来事があります。かつて僕は、胎児治療※で有名な聖隷浜松病院のNICU(新生児集中治療室)で研修をしていました。
※胎児治療:出生前の胎児の病気や障害を、母体を通してまたは一時的に体外に取り出して治療する方法
ある時、内視鏡を用いた胎児治療を行っている最中に、お腹の中の赤ちゃんの心拍が低下してしまう事態が起きました。その際、蘇生処置のために呼ばれたのは小児科の先生でした。
その光景を見て不意に、「まだお腹の中にいる『胎児』なのだから、これは産科医が対応すべき領域ではないか」「小児科医が行う治療は、産科医もできなければならないのではないか」と疑問を抱きました。
この出来事をきっかけに、「生まれてから診るのではなく、生まれる前から診ていこう」「胎内でできる限りのことをしていこう」と視野が大きく変わりました。それから、出生前診断や超音波検査(エコー)で、どこまで詳細に胎児の状態を把握できるかという分野にのめり込むようになりました。
現在、当院では出生前検査・超音波検査・遺伝学を組み合わせてトータルに診ていくことを大切にしていますが、そのライフワークとなる診療方針が確立されたのは、あの日、胎児治療の現場で感じた「気づき」がきっかけだったと思います。
クリニックの二大柱「出生前検査」と「無痛分娩」
――「出生前検査」と「無痛分娩」がクリニックの特徴とお伺いしました。特に「胎児ドック」とはどのような検査なのでしょうか
当院では、生まれてくる前の胎児の状態を診る「出生前検査」に力を入れています。「胎児ドック」とは、一般的に「胎児精密超音波検査」と呼ばれるもので、妊娠初期にあたる12〜13週頃、赤ちゃんがまだ6〜7cmほどの時期に行う詳しいエコー検査のことです。
近年、エコー機器の性能が向上したことで、早い段階から様々なことが分かるようになってきました。これは世界中で行われている「妊娠初期のスクリーニング」なのですが、日本では「胎児ドック」という名称で普及しています。
具体的には、赤ちゃんの首の後ろのむくみ(NT: Nuchal Translucency)の厚さや、鼻骨、静脈管や三尖弁の血流、心拍数などを計測し、染色体異常のリスクを推定します。なお、これはあくまでリスクを判定する検査ですので、確定診断を得るためには、別途、羊水検査や絨毛検査などを行う必要があります。
このNT測定を正確に行うためには、イギリスの財団(FMF: The Fetal Medicine Foundation)が認定する国際的な資格が必要で、毎年測定データを提出して更新しなければなりません。その中でも、測定経験が豊富で一定の技術レベルを維持している者は「スペシャリスト」として認定されます。
日本国内でこのスペシャリストに認定されているのは44名のみです(2025年10月現在)。僕もその中の一人として認定を受けていて、昨年にはついに「永久ライセンス」を取得することができました。


――先生のクリニックには、その胎児ドックを希望されて遠方から来院される方も多いそうですね
そうですね、実際に受診される方の約半数は、当院以外に通院されている方や、県外からお越しになる方々です。
当院では胎児ドックだけでなく、NIPT(新型出生前診断)など、あらゆる出生前検査に対応していますので、患者さんご自身の希望に合わせて検査を選択できるのが大きな特徴です。
スクリーニング検査から羊水検査などの確定診断、そして分娩に至るまで、妊娠初期から一貫して対応できる体制が、患者さんの安心感につながっていると考えています。
――もう一つの柱である「無痛分娩」についてはいかがですか
当院では、妊婦さん一人ひとりの考えを尊重して、分娩方法の大切な選択肢の一つとして「無痛分娩」を提供しています。無痛分娩を希望される方は、ここ最近で確実に増えていると感じますね。
一人の女性が出産する回数が少なくなっている分、一回一回の出産が持つ意義はますます大きくなっています。また、多様性が尊重される現代において、お産の「痛み」に対する考え方が人それぞれであるのは自然なことです。
三重県内では、24時間体制で無痛分娩に対応できる施設は限られていますので、その点は当院の大きな強みだと考えています。
不安なことは、何でも気軽に相談してほしい
――これから妊娠・出産を控える読者の皆さんへメッセージをお願いします
患者さんの中には、色々な悩みを抱え、なかなか言い出せずにいる方もいらっしゃいます。昔のように、質問したら怒るような先生は今はほとんどいないと思いますので、どんな些細なことでも、不安に思うことは産院で気軽に相談してもらえたらうれしいです。
疑問や不安を解消して、安心して出産に臨んでほしいですね。

――先生ご自身のリフレッシュ方法は何ですか
エコー検査が趣味と言えるほど、僕にとってはライフワークになっているので、普段の診療そのものがリフレッシュになっています。そのため、仕事でストレスを感じることはありません。
仕事柄、なかなか遠出をすることは難しいですが、休日に家族と過ごす時間はとても良い息抜きになります。子どものサッカーの試合やバンドの発表会を観に行くことが楽しみですね。
先日も、家族でバンドを組んで発表会に参加しました。僕がドラム、妻がキーボード、子どもたちがボーカルやギター、ベースを担当して演奏しました。こうした家族と過ごす時間が、何よりのリフレッシュになっています。
(取材:2025年12月)
※ 本記事は、取材時の情報に基づき作成しています。各種名称や経歴などは現在と異なる場合があります。時間の経過による変化があることをご了承ください。